この記事は約 11 分で読むことができます。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
皆さんは、耳もがんになることがあることをご存知ですか?
耳のがんは聴器がん、外耳道がん(がいじどうがん)などと呼ばれています。聴器に発生するがんですが、がんの中では「希少がん」にも分類され、発症する頻度は極めて稀ですが、100万人に1人の割合で発症すると言われています。
耳の前(耳前部)から下(耳下部)にかけて「耳下腺」という臓器が存在します。これは唾液を産生、分泌する臓器のことで、普通は耳下腺部を手で触れても臓器の存在を感じ取ることはできません。耳下腺の中には、顔の筋肉を動かして表情を作ることができる顔面神経が通っています。
この耳下腺に発生した腫瘍(できもの)を耳下腺腫瘍と言い、その中でも悪性のものを聴器がん(外耳道がん)と呼んでいます。日本で1年間に行われる良性の耳下腺腫瘍の手術がおよそ6000件、良性腫瘍と悪性のがんの比率はおよそ10対1と推定されています。
聴器がん(外耳道がん)は、新規に診断される人が、毎年10万人当たり6人未満と非常に少ない希少がんだと言えます。
今回は聴器がん(外耳道がん)の原因、診断基準、治療法などについて特集します。
聴器がん(外耳道がん)とは?

聴器とは聴覚に関連する臓器のことで外耳、中耳、内耳に分けられます。頭頸部領域のがんの1%から2%程度を占めています。発生する場所としては外耳が最多で、次に中耳で、内耳にはがんはほとんど見られません。
がんの場所が深部に位置すればする程に治療前に診断がつきづらいという大きな特徴があると言えます。良性疾患として治療を受けた後に、実際は聴器がん(外耳道がん)だったと判明するケースもしばしば認められ、診断が困難な疾患の1つとして挙げられます。
症状は、耳鳴り、耳の圧迫感、違和感、耳だれ(耳から分泌物が出る)、耳痛、耳出血、耳閉感(耳が塞がった感じ)や聴力低下(難聴、聞こえづらい)などが現れます。
耳だれは、耳から血や、血が混ざった耳汁が出る症状のことです。正式には出血性耳漏(しゅっけつせいじろう)と言われています。持続する耳の痛みと出血性耳漏の2つが確認された時には、聴器がん(外耳道がん)である可能性もあると考えた検査を実施します。
耳の痛みが長い期間持続し、次第に症状が強くなっていく傾向です。外耳炎による耳の痛みは、抗生物質などの適切な投与で次第に落ち着くことで、1~2週間程度で治癒します。痛みが何ヵ月も続く時や増強していく時には注意が必要となります。
その反面、悪性の病気である外耳道がんの耳痛(:じつう)は数ヵ月と長く継続し、非常に強い痛みまで進展していきます。
進行がんでは顔面神経麻痺、口が開けづらくなる開口障害、腫瘤形成などの症状があります。顔面神経麻痺は顔の左右片方が上手く動かなくなり、目がきちんと閉じられない、口元から水がこぼれる、などの症状が出現します。顔面神経麻痺のほとんどは耳下腺がん以外の原因によるものですが、耳の前、下辺りの痛みやしこりを伴っている時には注意が必要となります。
開口障害とは、耳の側に顎関節があることで、腫瘍がある時には口が開きづらくなることもあります。がんが顎関節付近に広がっていることもあって、開口時の痛みなどに関しても診察で確認されます。
聴器がん(外耳道がん)は非常に珍しいがんであることで、良性疾患でも同じ様な症状が現われることで、外耳道の良性腫瘍や外耳炎と診断を誤診されやすい疾患だと言えます。
癒着、痛み、顔面神経麻痺のそれぞれの症状とも、聴器がん(外耳道がん)の悪性度が上がっていくと、その発生頻度が高くなるという実態調査もあります。
聴器がん(外耳道がん)は腺様嚢胞がん(せんようのうほうがん)、扁平上皮がん(へんぺいじょうひがん)、基底細胞がん(きていさいぼうがん)などの組織型がありますが、発生頻度は扁平上皮がんがおよそ70%を占めます。
進行する症状がある時には、耳鼻科で精密検査を受けることが鍵となります。
▽原因

聴器がん(外耳道がん)を発症する原因の1つとして、「慢性的に持続する炎症」が挙げられます。聴器の慢性的な刺激と炎症は、代表的なリスク因子で、耳かきを使った耳掃除が挙げられます。
耳掃除に関しては、アメリカの耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会(AAO-HNSF)も耳を損傷するリスクがあるとして警告を出しています。
本来、外耳道には細かな毛が生えていて、不要なものを外へと排出する自浄作用を持ちます。
ですが、硬いスプーン状の耳かきなどを使った耳掃除により細かな毛を弱らせたりしてしまうと、自浄作用は働きづらくなって、耳垢などが自然に排出されなくなっていきます。そのため、かゆみなどを感じて、繰り返し耳掃除を行って外耳道の上皮を傷付けてしまうという負のループに陥ります。
この理由から、硬いスプーン状の耳かきを使った耳掃除は、今からでも控えて頂いた方が良いと考えられます。
どうしても外耳道のかゆみなどが気になる時には、硬いスプーン状の耳かきを使わず、耳掃除をする時に、お風呂上がりなどに柔らかい綿棒で拭き取るのが良いでしょう。
本来、耳掃除が必要な人は、耳垢に粘り気がある湿性耳垢(しっせいじこう)の人のみです。ですが、湿性耳垢の人の場合は、耳鼻科での耳掃除が必要になることで、いずれにしてもご自身での耳掃除は推奨できません。
聴器がん(外耳道がん)は頭頸部がんの中の1つとして分類されますが、頭頸部がんは世界的にみると、決して珍しいがんというわけではありません。例を挙げると、歯科が普及していなくて口腔衛生の維持が困難な地域や、噛みタバコが普及している地域などでは比較的多く患者がいます。
このことで、頭頸部がんの発生には環境的素因が関わっていると想定されています。
▽診断基準
画像引用・参考:聴器がん(ちょうきがん) 国立がん研究センター 希少がんセンター(2024年)
今までの経過をよく確認した上で頭頸部領域の診察を実施し、がんが疑わしい場合には画像検査を行います。一般的にはCT検査を実施しますが、必要に応じてPET-CTやMRIを追加して病変の広がりや深さなどの進展範囲を解析します。
腎臓の機能やアレルギーの問題がなければ、MRI、CTでは造影剤を活用します。これらの画像検査で、病変の広がりや大きさ・頸部リンパ節への転移・全身への転移を総合評価し、ステージ(進行度)が決定されます。
最終的な診断には、病変の一部を生検することが必須になります。一回の生検では聴器がん(外耳道がん)の診断がつかないこともあるので、症状が長く持続したり、疑わしい場合には繰り返し生検を行うことが大事です。
▽ステージ分類

聴器がん全般のステージ分類には、“Stellによる外耳道・中耳がんに対するT分類”というものがあります。
しかし、外耳道よりも深い部分である中耳のがんは発見が難しく、多くは相当に進行してから初めてみつかります。
そのため、現場において実際に役立つステージ分類は、聴器がん全般ではなく外耳道がんのステージ分類である“Pittsburgh分類”といえます。
画像・引用:聴器がん(耳のがん)とは 東京がんクリニック
▽治療法

聴器がん(外耳道がん)は各医療機関の報告が少数例であること、さらに病変の広がりも患者さんによって多彩であることで、それ以外のがんと比較すると明確な治療戦略が定義されていないのが現状です。現在は外科的切除をメーンとした治療が一般的で、化学療法や放射線療法は補助的な意味合いで選ばれます。手術が行えないケースについては、最初から手術や抗がん剤治療など化学療法・放射線治療を実施する場合もあります。
◉手術
早い段階での聴器がん(外耳道がん)では、第一に選択されることが多い治療法です。早期に見つかった聴器がん(外耳道がん)であれば、切除の範囲が小さく、術後の機能障害も比較的少なくて済みます。また、耳の後ろを切開することもあって、手術した後の傷はほとんど目立ちません。手術をした後しばらくは定期的な耳の処置が必要となります。
◉抗がん剤治療
最近の治療薬の開発の発展の状況を受けて、多くの種類の抗がん剤を使うことができる様になりました。免疫チェックポイント阻害剤(キートルーダ、オプシーボ)を使用した最新の治療で、手術が受けられない様な進行がんであっても、長期生存ができる様になった患者さんもいます。
◉放射線治療
進行がんに対する手術は、かなり広範囲の切除になることで、手術した後の機能障害が問題となります。そのことから、機能温存の目的で、放射線治療が選択されるケースが少なくありません。化学療法(抗がん剤治療)を放射線治療とかけ合わせる場合もあります。その際の化学療法の投与方法として、動脈からカテーテルを挿入し、腫瘍を栄養する血管に抗がん剤を直接送り込む超選択的動注化学療法が併せて用いられる場合があります。
放射線治療は、IMRT(強度変調放射線治療)が導入されていて、これまでの方法より合併症の減少や腫瘍制御率の向上が期待が持たれています。また、放射線治療は手術をした後の補助療法としても使うことができます。
手術は外耳道の骨を切除するだけで済むケースもあれば、顔を動かす顎や神経の関節を一緒に切除しなければいけないケースもあります。さらに大きな切除を必要とする場合は、開頭手術(側頭骨(そくとうこつ)亜全摘)を行う場合もあります。開頭手術は腫瘍を残さないことが治癒率や治療成績に大きく関わることから、大きな腫瘍であればあるほど切除範囲が大きくなり術後の機能障害も大きくなってしまいます。腫瘍の進展範囲を正確に診断して適切な切除を実施することが重要です。
▽予防策

聴器がん(耳下腺がん)もそれ以外の多くのがんと同じ様に、早期発見、早期治療が非常に重要となります。耳の前、耳の下に触れて、しこりの様な腫瘤を感じ取れた場合は耳下腺腫瘍ができていると疑われます。
その上で痛みを伴ったり、耳下腺腫瘤がどんどん大きくなったり、顔面麻痺の症状が出現した時には注意が必要となります。早期に近くの耳鼻咽喉科頭頸部外科の医療機関を受診して下さい。

参考サイト
唾液を分泌する耳下腺に生じるまれながん 「耳下腺がん」とは?
耳にできる聴器がんの原因と症状-耳掃除に注意 メディカルノート(2018年)
「聴器がん」を疑う初期症状・原因・生存率はご存知ですか?医師が監修! メディカルドッグ(2023年)
怖いなと感じる
この記事を書いたきっかけは、家で、毎週決まった日に、病気や障害、難病などについて特集しているラジオを、母はコーナーが始まった当初からそのラジオを聴き始めたことでした。
私も今年に入って、そのラジオを聞き始めました。
この聴器がん(外耳道がん)に関しては、私が聞いておらず、母から「耳掃除のし過ぎでなるがんがあるらしいよ」と聞いて、そこから書いてみようと思って書き始めました。
他のがんより希少がんなためか、他のがんと一緒に検索に引っかかり、それでもそれに特化したところが少ないなど、いかに余り知られていない、極めて稀ながんだと、検索のボリュームからも分かりました。
検索にはあまりひっかからなくても、がんである以上、誰でもなる可能性がある。
情報の少なさから、ステージが進行するまで、がんを見落とす可能性がある。かなり怖いことだと感じます。
正直耳掃除のし過ぎでがん化するとか、普通は考えないことでもあります。
この記事を書いて、がんにならない臓器はないんだなと、絶望しました。
この記事が聴器がん(外耳道がん)を知らなかった方にも、注意できる、そんな警鐘を鳴らす記事になれたらと、強く思っています。

noteでも書いています。よければ読んでください。
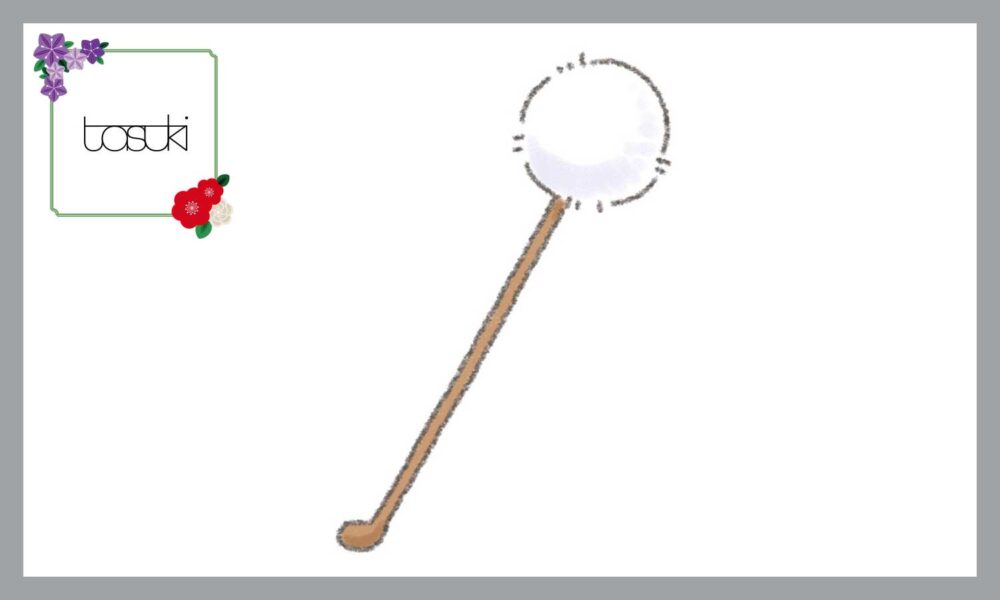




















コメントを残す