この記事は約 5 分で読むことができます。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
私はリカバリーストーリーの中で書きましたが、2025年2月に好きなアーティストのライブに、2年ぶりに行って参りました。
去年は抽選に外れて、2年ぶりに参加しましたが、2年前より会場が広くなっていました。行くまでが遠くて、それだけでも疲れていたのですが、会場に着いて、「トイレに行っておかなきゃ」と思って行くと、そこでも人が多かったです。
開場がギリギリになって、スタッフの方に席に誘導して貰い、座るとすぐライブが始まって、そこからずっと立ちっぱなしで疲れ果てました。
楽しかったですが、2年前より体力の低下を感じたのと、疲労感がその次の日の週はなかなか抜けなかったですね。
ライブもアリーナが多そうなところだったのに、結果はスタンドの後列で、自分の席運の無さを感じました。
そんな大変な想いをしても、いつも笑顔と元気を届けてくれる推しのアーティストに感謝して、今日も記事作成を頑張っています。
ライブが終わって、1ヵ月以上が経過しましたが、元気をくれる、障害者のアーティストも世界にはいます。
韓国には、難聴など聴覚障害を抱えながらも、アーティスト活動をしている人たちをご存知ですか?
2024年4月にデビューをした韓国の3人組アイドルグループ、『Big Ocean』(ビッグ・オーシャン)が2025年3月、愛知県豊田市で今回のツアーでは1回限りの日本初公演を行い、お客さん達と一体感のあるパフォーマンスをお披露目しました。
『Big Ocean』は3人とも難聴がありますが、障害を感じさせない、手話と歌を交えたお客さん達とのコミュニケーションでステージを熱狂させました。
今回は、『Big Ocean』のメンバー構成、どうやってダンスなどを覚えているの?などを発信したいと思います。
難聴のある『Big Ocean』の3人。ダンスを覚えるために使っている道具などは?

Big Oceanは、パク・ヒョンジン(25)、キム・ジソク(22)、イ・チャンヨン(26)の3人組。補聴器や人工内耳を装着して、聴者との会話をしているという。メンバー同士では周囲に騒音がある時は、手話も交えて情報交換しているそうだ。
ダンスで動作を合わせる際、音楽に合わせてモニターにタイミングを表示させたり、スマートウォッチを用い、振動で拍子を共有したりするなどの工夫をしているという。
引用元:読売新聞 聴覚障害の若者3人の韓国グループ、Big Ocean日本初公演…観客と視線を合わせて一体感(2025年3月21日公開)
ライブ後の後悔と感謝
私は、2025年2月に、推しのアーティストのライブに行って来ました。
2年ぶりに参加して楽しかったのですが、色々後悔もありました。
2年前より、会場が大きくなったことで、行くまでが遠かったです…。バスもなかなか来ず、「果たして、ライブ時間までに間に合うのか?」と不安になりました。
会場に着いたら、広すぎて、開演時間に入って、始まる前から、バタバタしていました。
大きな会場だからこそ、隅々まで音を届けないといけません。
「こんなにダイレクトに音が届くんだ」と、その日から耳がどこか不調になりました。
ライブの音が大きかったためか、低音が行く前より、聴き取りづらくなりました。
行って、「もう最後のライブかな」って思うのですが、今は全くエンタメごとには行かないので、チケットの申し込みが始まって、当たれば、行ってしまいます。本当に意志が弱いです。
耳が不調になって、後悔しているところもありますが、感謝をしているところもあります。
特に音楽活動以外もしているアーティストさんは、予め決まっていたライブ日程に、突然イレギュラーな仕事も入って来ます。
私は一人で参加するので、エンタメごとに行く時、他県には出たことがありません。
ライブなどは遠征する人もいますが、私みたいな地元であるライブは今回が最初で最後の参加という人もいます。
アーティストの方は、それを知っていると思います。
なので、イレギュラーな仕事が入り、スケジュールパンパンで、過労で心身がバテバテでも、精一杯ライブでの自分もファンに届けてくれる。本当にプロフェッショナルな方が多くいます。
昨今のエンタメ業界は昔より大変なスケジュールも多く、身体的な不調や心の不調、アーティストだったら、耳や声帯など喉の不調も大いにあります。
頑張っている姿に励まされますが、「無理、し過ぎてませんか?」と、不安を感じる日もあります。
本当にステージに立ち続けてくれる姿はキラキラしていますし、感謝もします。
息詰まる世界だからこそ、音楽や頑張っている姿に背中を押して貰っています。
本題の『Big Ocean』さんは知らないアーティストさんでしたが、私と同じ様に励まされているファンも多いと思います。
聴覚障害を抱えていても、アーティストをされていらっしゃるところが珍しいなと感じました。
音楽は言葉も国も越えていく。
それを私も再度、自分の推しのアーティストを通しても、この記事からもそう感じました。

noteでも書いています。よければ読んでください。
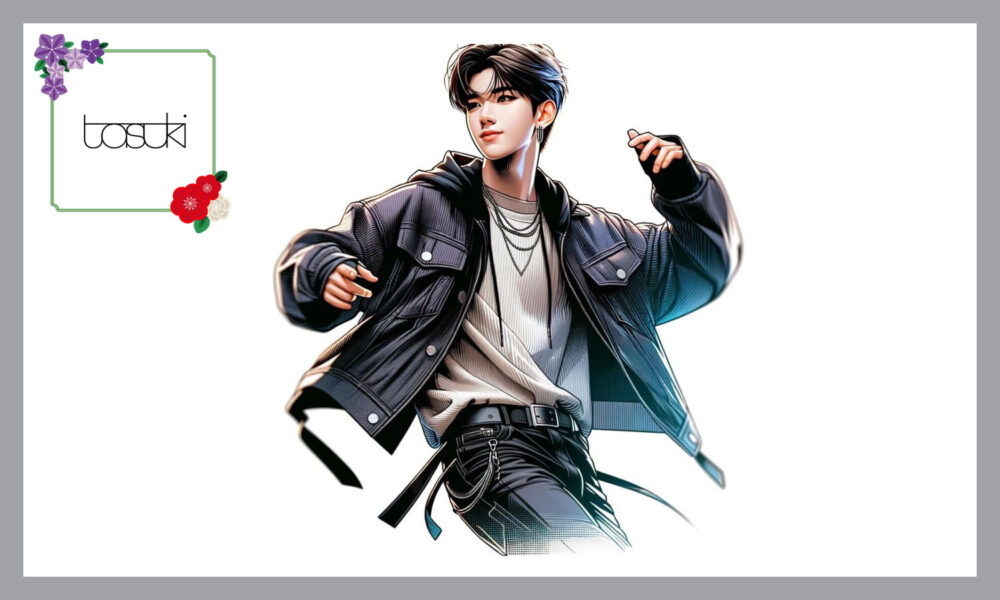




















コメントを残す