この記事は約 17 分で読むことができます。
この度、障害者の方にインタビューをして、支援の在り方や当事者の声を大事に反映されながらインタビューに取り組まれている、Webメディア『Inclusive hub』を運営する深宮様に、インタビューをする機会を頂戴しました。
前編では、『Inclusive hub』を立ち上げたきっかけ、インタビューに取り組まれる時の姿勢。経済産業省でお仕事をされていた時に行なっていた、ドローンを安全飛行するために、日本で最初に事業に携わったことなどについての興味深いお話をたくさん伺うことができました。
前編の記事はこちらです→
後編では、それ以外の関連のお仕事について、また今後の『Inclusive hub』の活動の展望についてお話を伺わせていただきました。
今回お話を伺ったのは、翼祈、ゆた、島川です。ぜひ前後編併せて最後までご覧になってください!
これまでの深宮様のお仕事について

翼祈:3年間、インドでの外交官時代は、今の様な福祉関係に携わっていたのですか?
当時は全く関わっておりませんでした。当時は、日本と中国の外交関係が緊張した時代だったので、「チャイナプラスワン」という、中国の次にどの国に行くんだ、という時に、候補の一つが市場の大きいインドでした。
本当に毎日のように日本の有名な企業の社長さんが来るような時代だったので、そういう方々がビジネスをインドで成功させるためにできるだけ支援する、そういった仕事をしておりました。
翼祈:秘書の立場から学ばれた、“永守経営”とは、どの様な経営方針ですか?
永守経営は、彼の言葉を借りると、「気概と執念」と彼は常に言っていて、いい意味で「頭で考えるよりも、本当に自分でやりきるつもりがあるんだったらやりきれ」みたいな話ですね。その考え方が1番大きかったかなとは思います。
翼祈:スタートアップのピクシーダストテクノロジーズと出逢ったきっかけを教えて下さい。
出会ったきっかけは、障害とか高齢者とか、身体や心が不自由な方が増えていく中で、そういう課題解決に貢献できることをしたいという話をずっとしてる中で、たまたま出会ったのがピクシーダストテクノロジーズという会社でした。
翼祈:高齢者・障害者向けを主なフィールドに、自動運転車いす、認知症と五感刺激、難聴者、聴覚障害者向けコミュニケーションデバイスなどを提供されていますが、それぞれどの様なサービスで、どんなメリットが当事者の方にあるか、教えて下さい。
これらは、ピクシーダストテクノロジーズ時代にやってたものです。聴覚者障害者向けのコミュニケーションデバイスは、元々一緒にやっていたチームメンバーの義理の弟さんが「聴覚障害」であったことがきっかけです。私はその時、初めて「聴覚障害」の方と出会いました。
例えば、補聴器は、一対一の会話にはすごく強いですが、例えば集団で集まった時など、ディスカッションのように色んな方向からの会話が交ざるケースの時に補聴器だとどうしても聞こえが悪くて、会話に入っていけないと聞きました。
では、どうするのか?ということを考えた時に、最初は「メガネのようなレンズ上に声を文字化して表示できないか」と発想しました。最終的には、パソコンやタブレットの画面上にどの人がどの方向から何を喋ってるかが同時に文字として現れる形になりました。
自動運転車椅子は、プロトタイプ止まりで終わりましたが、解決したい課題は介護施設の人手不足でした。人手不足で、入居者が外に出たり、散歩に行くことが自由できなくなってしまう。
入居者の側も気にしてしまって、自分を連れてってくださいとか、忙しそうな人に対して言えないよね、ということがあって、別に誰かが押さなくても外に出れられる『自由に動けるという自由』というものを少しでも提供できないか?という意味でやっていっていました。
翼祈:精神疾患サポートというのは、全ての精神疾患に対してでしょうか?サポートを受けた当事者からは、どんな声が届きましたか?
精神疾患向けのサポートもピクシーダストテクノロジーズ時代に考えた件ですが、これも上市できずに終わりました。当時は、「統合失調症」をメインで考えていました。
「統合失調症」のある息子さんを持つお母さんと一緒にこういうことができないかと開発したり、国立精神・神経医療研究センター(NCNP)というナショナルセンターの先生にも、アドバイスをいただいたりしていました。
翼祈:養成研修一般過程を修了された同行援護従業者とは、どんな資格なのか教えて下さい。
これは「視覚障害」のある方が外出する際に、同行援護を実際に提供できるようになるための資格で、国家資格ではありません。自分自身が「視覚障害」のある方に多く会うようになって、その中で自分ってあまり分かってないなというのもあるし、実際その人達と歩いてみたいなと思って、資格を取得しました。
翼祈:東京都の多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」とは、どんな事業でしょうか?なぜ、参加しようと思われたのでしょうか?
東京都は、東京を世界一の起業大国にしようと凄く力を入れていて、その一環で、起業を支援する50社が東京都とパートナーを組んで、多様な分野で起業を増やそうという取り組みが「TOKYO SUTEAM」です。現在の株式会社The Elementsが、その50社の一つに選ばれました。
元々、自分自身がスタートアップにいながら、スタートアップに求められる高い成長が難しい障害などの分野に取り組んでいたこともあって、その分野に取り組む難しさも知っていたので、少しでも支援できないかということで、応募してみたところ、選ばれました。
翼祈:過去に9回開催されたミートアップには、どうやって参加できますか?また、参加された方の印象に残った声を教えて頂きたいです。
「TOKYO SUTEAM」の事業の一環で実施したミートアップですが、残念ながら、事業自体が3月末で終わってしまったので、今は実施していません。
私自身は、特定の障害の特定の課題を解決するために活動している組織ではありません。ただ、そういった活動をされている皆さんは、自分が関係する障害には関心が高くても、関係しない障害のことはあまり知らなかったりする場合もあります。
そういう部分を横断的につなぐことで、「他にこういう方もおられるんだとか、隣の障害が知れた、あそこの障害が知れた」っていう、お声をいただいたのが少しお役に立ったかなと思っています。
その他の活動について
翼祈:2025年2月に開催された、“ チャレスポ!TOKYO “とは、どんなイベントだったのか、教えて欲しいです。
チャレスポ!TOKYO自体がどれほどの歴史があるのかは分かりませんが、いわゆるパラスポーツを障害のある方も障害のない方も一緒に楽しもうというイベントを東京都さんが力を入れてやっています。
その中で、我々は全然スポーツとは関係ありませんでしたが、「障害のある人の課題解決にチャレンジすることを応援しているなら、ブースを用意するので、ぜひ参加しないか」というお声がけをいただいて、昨年参加しました。
今年は障害の分野の課題解決に取り組む色んなスタートアップや大学の研究室の方に出展いただく形でコーディネートをさせていただきました。
翼祈:“ チャレスポ!TOKYO “内の、「パラ×テクノロジー体感展」で、特に力を入れたポイントも教えて下さい。
まさに、「体感できるものを増やしたかった」という想いでいました。 例えば、視覚障害のある方の中には光だけ感じられる方がいる。真っ暗な中で、光で相手がどこにいるかわかれば、それを見て、ボクシングのパンチを繰り出すことができる。
そんなことを子供達にも感じてもらって、真っ暗で怖いんだけど、こいう世界に暮らしてる人がいて、この人達がスポーツをやったり、遊んだりするには、こういう工夫をすればできるるんだ、ということを分かってもらうことを凄く大事にしました。
それ以外について

翼祈:私は、ヘルプマークを着けています。ある日、駅員さんが私に、他の席が空いているのに「車椅子の付き添いの方が座るために、席を譲って下さい」と言われました。
ヘルプマークは、最近高齢者の方も着けていたりと、認知が上がっていますが、広く浸透していても、世の中の人には浸透しないように感じます。その乖離は何故だと思いますか?
「ヘルプマーク」は、付けてる人がかなり多くなったなって思っていて、それ自体は良いことだと考えています。例えば、電車で妊婦さんを見る確率と「ヘルプマーク」を見る確率はどっちが高いんだろうとか思うと、「ヘルプマーク」のほうが高いのではないかと感じるぐらい。
浸透すること自体は凄く良いと思いますが、一方でそれだけでは、その方がどんな障害をお持ちで、その方に対して何をどう配慮していいか分からない人も多いのではないかと思ったりもします。例えば、障害ごとに「ヘルプマーク」の色を変えるべきじゃないか、という意見の人もいました。
普及したのはいいことでしたが、今度は別の新しい課題が出てきているんじゃないかなという気はします。
翼祈:盲導犬を連れた視覚障害者の方が、お店に入店するのを断られるケースが後を絶ちません。視覚障害者、お店側、お互いが納得できる様になるには、私たちは何をしたら良いと思われますか?
基本的に性善説に立つのであれば、まだまだ知らない人が多いんだろうな、ペットなのか、ペットじゃないのか、みたいな区分けもなかなか頭ではできないみたいなことになっているんだろうな、とは思います。ただ、「そんなことも知らないのか」と言っちゃうと、広がらないなと思っています。
その人達が自然と「あっそういうもんなんだ」、「それは知らなかった、申し訳ないです」って、うまく意識を変えられるような啓発なのか。
そういった批判ではなく、「このお店ってこういうとこにも優しいから」ということ自体がお店に来る人を増やす宣伝になったり、いい意味で誘導ができればと思います。
そういう流れができるとお店も「あのお店がこういうことで評判が良くなっているから、配慮した方が良くない?」とか、別に視覚障害の人に限らず、「これ結構大事っぽい」とか「評価される」みたいにならないと、なかなかうまく行かないかなと思います。

翼祈:私は、AKARIで、「共生社会への実現を!」とよく書きますが、なかなか実現しているとは思えません。深宮様が考える、共生社会への実現とは、どんなことだと思われますか?
共生社会は、凄くいい言葉だと思う一方で、人によって凄く解釈が違い過ぎて難しいなって思う時があって、みんなどうなったら幸せなのかなとか、私も思っています。
共生社会って、なにがどうなってる世界がそれで、今なぜそれが実現していないと思いますか?
翼祈:障害者の方も言い分はありますし、健常者の方も言い分があって、その言い分が一致しないことで、乖離が生まれてる感じもします。先日インタビューした方に、「自分が障害者になるまで、障害者の方の気持ちが分からなかった」という話もありました。
SNSとかでも健常者の人で、「発達障害」とか「知的障害」を批判したりする方も多いですが、専門家の方とか精神疾患に詳しい方が書いてあるのが、「精神疾患とかは、誰でもなってしまう可能性がある病気です。今ならないと思っていても、何かのタイミングでなることもあります。」ということです。
例えば、過労で体を壊したり、うつ病などを発症して、休職してる間に他の人たちが仕事をしていて戻る席がなく、退職されるというケースもよく聞こえてきます。
健常者の方が精神疾患に対する偏見が凄く強いなと思いながらも、その方達にとって病気は「自分たちと関係ないよね」みたいなところを強く感じます。そういうことを言う方は、自分は障害者の方とは違うという思いが強すぎることで、苦労することもあります。
「うつ病」とかになった時に、自分がこうなると思わなくて、とても苦しい、もう本当に生活もできない、もう頭も体も起き上がらないって発信をされてる方も多いですが、本当に何もなかった方は、そういう方の投稿とかも読むこともないと思います。
障害者と健常者は結構、近くにいるようなものにも関わらず、特に健常者の方が障害者の方をもの凄い遠い存在、自分とは関係ない存在と扱ってることで、私とか障害者の人が共生社会の実現をと言っても、なかなかこう健常者の方に響かないのかなっていう気もしてます。
深宮さん:私が官庁で働いていた頃、同期にも、部下にも、「精神障害」になった方がいました。それで、今、振り返って申し訳ないなと思うことは、何か声を掛けてるつもりでも、芯の部分では分かっていませんでした。
今、これだけ、数多くの人のお話をお聞きして、それなりには理解できるようになったと思っていますが、 最後はどうしても、「なったことがないから、分からない」が真実だとも思っています。 簡単に分かったとは決して言えないです。
シンパシーとエンパシーという言葉があって、シンパシーは共感までいっても、エンパシーは理解までだと思っていて、別にその人のしんどいよね、と共感までいかなくてもよくて、「他人の靴を履く」というか、「せめてその人を理解する努力はしようよ」というところまでは持っていけないものか、と思っています。
私自身、「なんでそんなことやってるんですか?」「あなたは別に家族も自分も障害も何も関係ないのに何でやってるんですか?」って言われます。それ故に私は、障害を遠い存在だと思っている健常者と、障害のある当事者の間のどこかにいるのだと思っています。
全然関係なかった立場だけど、少しでも理解しようと思って、こういうことやってるというのが、繋がってくれればいいなと思っていて、みんながみんなに可哀想とかいうのって、変な社会だと個人的には思います。
理解するという、配慮をいかに持てるかというところが少しでも広がって、例え同情はしなくても、共に生きてますよという意味での共生社会になればいいのかなと、私は思っています。
翼祈:私が今の意見を聞いて、改めて思ったのが、周りに障害者の方がいなくて、健常者の方しかいない人達の中にいる方は、障害者の方って目を向けたら近くにいるのに、いないっていうような感覚があります。だけど、問題とか起こしたら、近くに住んでて怖いねという話になったりして、深宮様の言われてる、理解することが凄く大事なんじゃないかなと思いました。
最後に
翼祈:深宮様やInclusive hubが今後叶えたい夢や、将来の展望を教えて下さい。
今まで色んな方に色んなお話をお聞きして、世の中は今、課題を抱えてる人とそれを乗り越えた人というのがいて、乗り越えた人の経験って、今課題を抱えてる人にとっては、凄く貴重だったりします。
それが当事者会とかで、色んな助け合いにはなってるんだと思いますし、今別に何も関係ない人も、いつ障害を負うことになるか分からない。でもその時に今まで自分が無視していたような人達の先を行っている経験がいきなりほしくなったりするのだと思います。
そういった経験が流通するのはいいなと思うところはあって、過去にとても苦労した経験は、今直面してる人にとっては物凄い価値があるので、そこにお金がついてもいいんじゃないかなと思っています。
私は祖母から「人生プラスマイナスゼロだから」って言われたのが小さい頃から頭にずっと残っていて、「あんたは今、うまくいってるけど、あとで谷に落ちるから、気を付けなさい」みたいなこととか、うまくいってなくても、「あんた、後は、どうせ登ってくんだから、大して気にしてもしょうがないんだ」みたいな話をされたことがありました。
そのように、過去の辛かった経験が、将来お金になって報われることでプラスマイナスゼロになってもいいんじゃないかなとも感じています。
それが理由で、「あの時のことを話すのはしんどいけど、誰かの為になってるんだったら、ちょっと話してみようかな」とかアウトプットしてみようってなれば良いなとか最近思っていて、そういう経験の流通にも貢献できたら、面白いかなと思っています。
翼祈:この記事で初めてInclusive hubさん達のことを知った方もいます。AKARIの読者の皆さんに向けて、メッセージをお願い致します。
「AKARI」さんの記事はたくさんいいものがあると思うので、読んでいただきたいですし、そういう活動されてる方の少しでも応援になればと思います。うちのメディアを見てほしいというよりは、うちのメディアに載ってる人や活動を知って繋がってくれると嬉しいなって思います。
▶︎深宮様 関連情報
代表を務めるThe Elements HPとロゴマーク

Inclusive hub HP
~感想~
翼祈:元々『Inclusive hub』様を知ったきっかけは、当時Xにあった固定ポストから応募して、インタビューを受けて、そこから深宮様とお知り合いになることができました。
私自身の最近の体験だと、私がライターコミュニティに入っていて、2回目のコラムを書くことになっていて、凄くありがたかったのがプロのライターさん達からコメントがあって、「こんなに頑張ってる人がいるんですね」だったり、「勇気をもらえました」とか、温かい色んな言葉をかけていただきました。
また、「凄く魂のこもったコラムをありがとうございます」とか、そういう自分が想定しなかった反応をいただいて、自分の思いを伝えたら届くんだなということを感じて、その経験もとても嬉しかった経験でした。
本当にこれからも、色んな経験をしていきたいですし、自分の障害や病気のこととかも、深宮様が先程、苦労した経験を誰かの価値になるって言われてたので、これからも、発信して、もし、似たような境遇の方がいた時に凄く参考になるなとか、心が軽くなったとか何かの支援に繋がったとかそういう人が1人でもいたら嬉しいです。
そういう誰かを救えるような記事を書いて、「TANOSHIKA」の中で仕事と向き合って、届けていけたらいいのかなと感じました。 この度は、本当にありがとうございました。
ゆた:色んな分野でのお話が聞けて、本当に楽しい時間でした。最後のシンパシーとエンパシーの話で共感と理解ってところで、僕は統合失調症なんですけど、この病気になってない人から、「分かるよ、 辛いよね」って言われても、やっぱりどこか「本当かよ」って、思う部分もあったりして、共感って自分自信が体験してみないと分からない部分はどうしてもあると思っています。
ただ、理解してもらえることはあるんですよね。理解してもらえた時って凄く嬉しくて、自分の障害が誰かに、認められたわけじゃないんですけど、伝わったんだなっていうのが、嬉しくなったりします。
理解してもらった時には障害者側も感謝の気持ちを伝えるべきだなと思うし、理解されて当たり前だろっていう、傲慢な態度は、いち障害者として、してほしくないなって、思ってます。本日は ありがとうございました。
島川:今回、お話を聞いていて、僕は今の制度のサービスって限界があるなとは思っていて僕も最終的には、制度の外側にあるもので、何か作れないかなと思っているところがあったんですけど、今日の話を僕にとって資産になると思っていて、勉強させていただいたなっていうのが素直な感想でございます。
ドローンの話もとても興味深く聞かせていただいたのですが、バランスの天井じゃないですけど、この規制の難しいところをこうやって突破していくんだなというところが、凄く勉強になりました。
今後も色んな取り組みをされていくと思いますので、私たちも引き続き追わせていただきます。本日はありがとうございました。
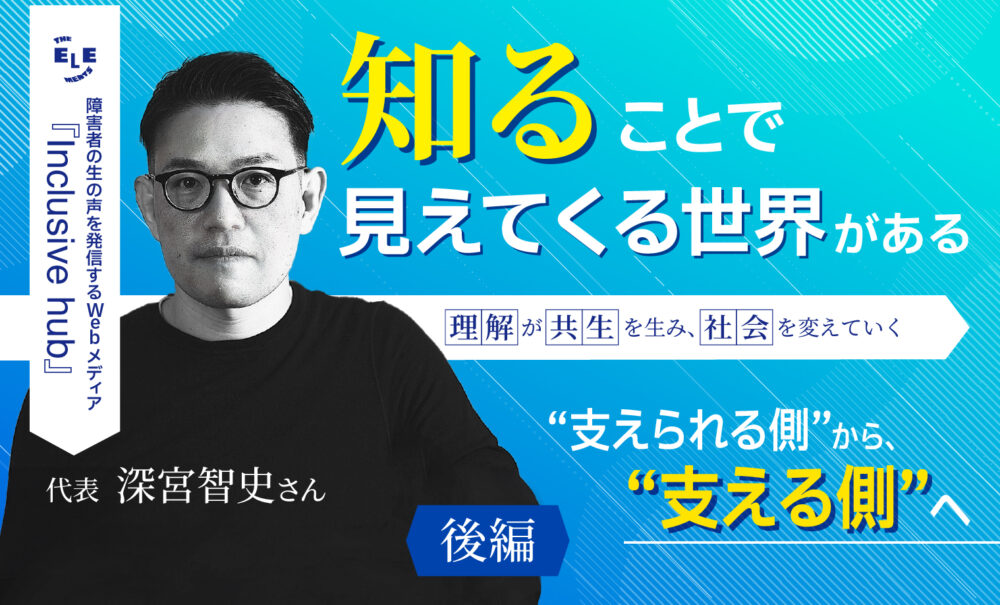
















コメントを残す