この記事は約 5 分で読むことができます。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
高齢者は前期高齢者と後期高齢者に分かれますが、一般的に高齢者は65歳以上の方を指します。
2024年9月時点で、日本の高齢者は、3625万人です。
私の両親も高齢者に入る年齢です。
母は料理の腕を磨こうと、スマホのアプリの検索結果に表示される料理のレシピをノートにまとめて、それを作ったり、改善点があれば改善して、また作ります。
父は、スマホこそ持っているものの、操作方法が分からず、メールやLINEのやり取りもできず、電話も上手くかけられず、YouTubeで動画を観るだけしかできません。
LINEも既読にすることもできない、アプリ自体も触ったことのない父ですが、東京都では、父も使えたらいいなーと思っている、LINEでの認知症予防のサービスがスタートしました。
今回は、『あだち脳活ラボ』のサービスが始まった1つのきっかけ、認知症のリスク測定はどんなものがある?などをお知らせします。
2025年3月から、東京都足立区は、主に65歳以上の区民を対象にした『あだち脳活ラボ』のサービスをスタートしました。LINEを使って、感性を刺激する美術や音楽、1000を超える脳トレや、同じタイミングで複数の動きをする体操など400本以上の動画が視聴できます。
『あだち脳活ラボ』のサービスがスタートしたコロナ禍というきっかけ。どんな認知症リスクが想定できる?

区が「あだち脳活ラボ」をリリースしたきっかけの一つは、コロナ禍だった。緊急事態宣言の期間中などに、各地で開かれていた体操教室などが中止に。自粛生活で、高齢者の運動や社会参加の機会が減り、体力などが低下する「コロナフレイル」が課題になった。
認知症のリスクも判定できる。「曜日や日にちがわからない」「ものの名前が出てこない」など13の質問に答えると、認知症のリスクを3段階で判定。50歳以上の利用者が最も高い判定になると、医療機関の検診案内をLINEで通知する仕組みだ。
引用元:読売新聞 認知症や介護予防へ自治体がスマホ活用、脳トレ・歩数記録…アプリ利用すれば店で使えるポイント付与も(2025年5月7日公開)
私の亡くなった母方の祖父は、認知症ではありませんでしたが、歳を重ねると共に動きが鈍くなりました。
母が高校生の時、同じ学校で、祖母の同級生のお子さんだった人が、お風呂の中で意識を失って、そのまま亡くなって、発見されました。
実はこのことは、私の祖父にも近いことがありました。
お風呂に入っている時、お風呂から出られなくなって、叔父さんや近所の人が祖父をどうにかして、お風呂から出しました。
それ以降、お風呂に手すりが付いたり、叔父さんが観ている時にしかお風呂に入れない様に、習慣化しました。
祖父が亡くなった年、まだスマホだけではなく、ガラケーも使うことができました。
祖父の年齢で、LINEなどを登録することはかなり難しいと思いますし、ガラケーだった祖母も特養ホームに入寮して、スマホに買い替えることなく、解約しました。
LINEの登録も叔父さんだったり、私の従兄弟だったり、祖父より若い歳の人が入れれば、登録できたと思います。
人は脳を使わないと退化するので、1000本を超える脳トレだったり、音楽などで、脳に刺激を与え、退化するだけではなく、若返らせることもできるのではないか?と感じました。
春になって、夏が近づいて来た最近の父の動き
父は、通常であれば1本ずつ生えてくるはずの歯が、特定の状況下で2本くっついて生えてきた「癒合歯(ゆごうし)」か、歯が重なって生えている状態「二重歯列または、叢生(そうせい)」で入り乱れて、歯が生えていたそうです。
元々顎が小さかったことから歯も小さく、かつ入り乱れて生えて、それがほぼ抜けて、さらに顎が退化してしまいました。歯がないので、食べるのに、時間がかかっています。
歯がないことや、煙草を吸う、乱れた食生活、夜勤の仕事、バランスの悪い睡眠習慣や夜更かしなどで、糖尿病も発症しました。
歯がないことで、口から空気が漏れ、スマホはスピーカーにしないと、相手に伝わらない位、上手く会話することもできません。いびきをかくなど、睡眠時無呼吸症候群も恐らくあって、口を開けて、いつも寝ています。
自分の行動を改めることなく、我が道を進む父ですが、流石に糖尿病になったことを気にしているみたいです。
母が、「畑の草が、1m位の高さになって、かなり荒れてるよ」と言っても、聞く耳を持たなかった父が、草取りを再開して、花などが咲いているのが、見える様になりました。
高くなり過ぎた木の枝を切ったりもしました。
そのことで、愛犬がいた時の様な1万歩動くことができなくても、冬より、糖尿病になった後は、意識的に動く様になりました。
甘いものもほとんど食べなくなりました。
腰の重い部分は変わらず重く、歳を取ったなと思いますが、それで少しでも次の血液検査で糖尿病の数値が良くなって欲しいなと強く思っています。
同じ疾患を20代前半から持つ娘の願いはそれだけです。

noteでも書いています。よければ読んでください。
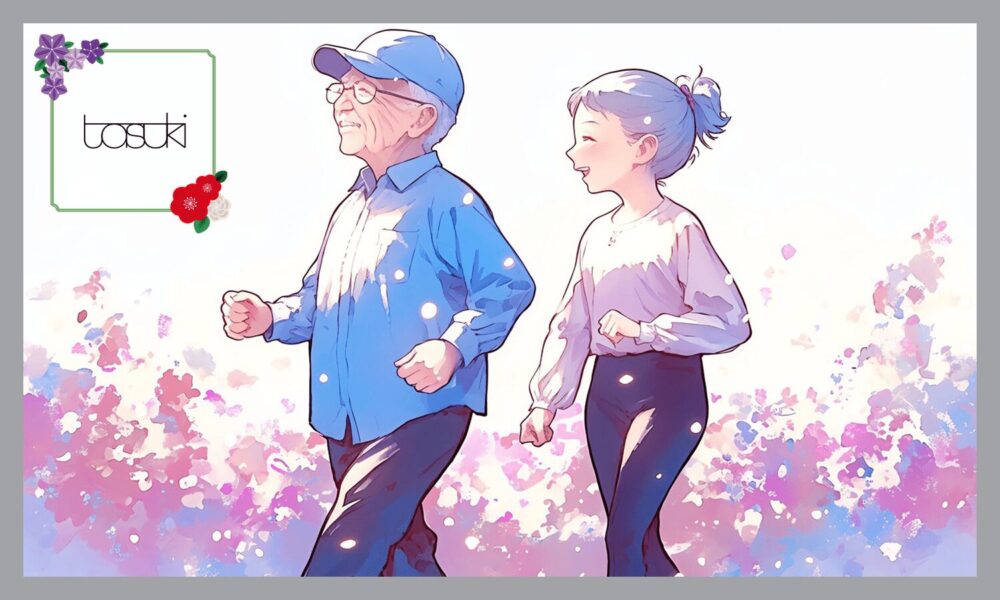



















コメントを残す