この記事は約 6 分で読むことができます。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
この記事をご覧の皆さんは、小児がんなどで小さい頃から入院し、手術を受けたり、「学校に行きたい」「友達に会いたい」と思って、治療を受けている子ども達の存在をご存知ですか?
そういう子ども達は病気などで体力が奪われている子も多く、感染症にもかかりやすいことで、特にコロナ禍の時は、家族ですら面会が叶わない時もありました。
何とか退院しても、すぐに以前の生活に戻るのは難しく、周りから配慮を受けながら少しずつ学校生活も取り戻していきます。
再発の恐れもあるので、本当にその子ども達やご家族の心身の負担は大きいものだと感じております。
病院ではその子達のために様々なプログラムが導入されていますが、その中の一つに、子ども達自らが自分の記録をビーズで残す、『ビーズ・オブ・カレッジ』という取り組みがあります。
『ビーズ・オブ・カレッジ』とは、入院中の患児とその家族への心のケアを目的とした「アート介在療法」で、アメリカで開発され、ヨーロッパやアメリカを主体に沢山の病院で導入されてきました。子ども達は治療の過程を色とりどりのガラスビーズを使いながら、自分のことを記録します。
具体的には、髪が抜け始めた時は顔のビーズ、輸血した時は赤いビーズなど、治療や処置ごとに決められたビーズを、ビーズ大使である医療従事者と会話を交えつつ、子ども達自身で繋いでいきます。
ビーズを繋いで、自分が病気を乗り越えてきた治療を振り返り、希望や勇気を肌で感じて、自分の人生に自信を持ちながら、自己肯定感を高めていけます。
2009年に『ビーズ・オブ・カレッジ』は、茨城県立こども病院で開始されてから、日本では2024年現在、29の施設で行われています。
今回は、『ビーズ・オブ・カレッジ』を考案したアメリカ人の方とは?、どういった効果を持つ介在療法?などを、説明します。
『ビーズ・オブ・カレッジ』は、どんなことで子ども達を励ましていますか?

ビーズは治療の記録。そして勇気の証。ビーズ・オブ・カレッジはアートを医療に融合させるプログラムの一つで、アメリカの小児腫瘍科で看護師勤務経験を持つジーン・バルーシ氏によって考案されました。重い病気と闘う子どもたちが自らの回復力や抵抗力を高められるように考えられた、人間の持つ治癒力に根ざした介在法です。

動画・引用元:tylershineonen The Beads become a source of pride – Dr. Hara’s interview(2012年11月2日公開)
勇気を与えるものだと思う
毎年2月15日の「国際小児がんデー」で、小児がんの支援や理解を発信する日として、世界中で啓発イベントが行われる日でもあります。
冒頭で書きました「学校に行きたい」と思う子ども達がいても、それを阻むものがあります。
小児がんは、年間2000人から2500人、新規に発症する子ども達のいるがんですが、医療開発が進んでいって、治療を受けた後、生存率は8割を超えていても、
退院しても外出が困難な子ども達に、自宅での療養が続いて、通学が再開できない子ども達への学習支援、自宅以外の場所での体験が可能な居場所の提供など、お住まいの地域の中で退院後の子ども達をどうサポートするかが大きな課題だといいます。
参照元:NHK NEWS WEB 小児がん 退院後に直面する課題 子どもたちをどう支えるか(2025年2月15日公開)
小児がんを取り巻くものとして、病院の中では、セラピー犬やファシリティドックなどが、動物介在療法(AAT)を取り入れている病院もあります。
外に出られなくても、病院で犬と触れ合うことで、勇気や笑顔を貰えて、元気になって、大人になる人もいます。
小児がんに関することで問題となっているのは、私が知っているものですと、
ドラッグ・ラグ(ドラッグ・ロス)や、晩期合併症です。
ドラッグ・ラグ(ドラッグ・ロス)は、海外では効果が認められ、その薬を飲めば治る可能性もあるのに、日本で薬事承認されていないことで、飲めずに亡くなってしまったり、個人で海外から直接高い金額を支払って購入している人もいる、社会問題です。
晩期合併症は、小児がんが完治しても、不妊や臓器障害など、放射線や抗がん剤の治療の後遺症で、様々な病気が出現してしまうことを言います。
小児がんも、治療を受けるだけでも大変なのに、退院した後も、様々な問題が浮上し、本当に生きているのも精一杯な方もいると思います。
『ビーズ・オブ・カレッジ』では、自分が受けた治療などのビーズを受けた後で、退院する前に完成したものを観て、「私、僕、こんなに治療、頑張って来れたんだ」と、実物があることで、本当に自己肯定感が上がります。
人は直接目に見える効果がある方が、その後も頑張ろうって思えますよね?
『ビーズ・オブ・カレッジ』は、2024年現在で29の施設で導入されていますが、まだまだこの取り組みは知られていないでしょうし、もっと導入しても良い施設が増えていいと思います。
この記事で、『ビーズ・オブ・カレッジ』を知って頂き、小児がんや重い病気で入院している子に、届いたら嬉しいなって感じます。
noteでも書いています。よければ読んでください。
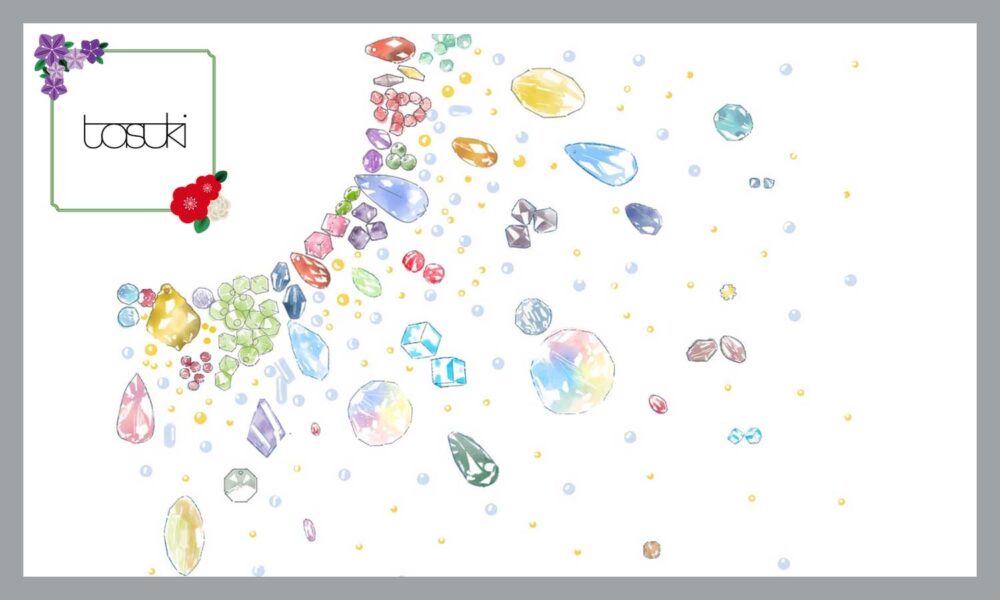























コメントを残す