この記事は約 21 分で読むことができます。
子どもを育てている/子どもを望む4組の同性カップルを追ったドキュメンタリー映画『ふたりのまま』の監督、長村さと子さんへのインタビューをこの度、させていただくことができました。
前編では、映画制作のきっかけとなった『生殖補助医療法案』への危機感や、当事者として感じる「責任とプレッシャー」について深く伺いました。
後編では、話題を映画の外へ広げ、監督の活動の根源に迫ります。
今回の特定生殖補助医療法案についてのお考えや、同性カップルの家族形成に与える影響、カミングアウトについて、長年にわたり「こどまっぷ」の代表として活動されてきた中で直面した課題、そしてその活動を突き動かす監督の揺るぎない「想い」に注目します。
同性カップルが子どもを持つ未来を「当たり前の選択」とするために、長村監督が見据える今後の活動予定や、読者の皆様へのメッセージもご紹介します。
家族の多様性や法制度について私たちが何を考えるべきか、そのヒントが詰まった後編も、ぜひ最後までご覧ください。
今回の特定生殖補助医療法案についてのお考え

©一般社団法人こどまっぷ
Pink:今回の特定生殖補助医療法案についてどう思いますか?
私自身は法律ができることには、反対していません。
第三者の卵子・精子提供を受けて生まれた子供が、自分の出自について知る権利をちゃんと持てるようにしてほしいし、それを「国としてちゃんと管理できます」というのであれば、とても素晴らしいことだなと思ってます。
法律がないと無法地帯化するというのは事実ですし、何より「生まれてきた子供達が出自を知る権利」を訴えてる人達にとって必要なことです。
子どもの立場から声をあげている当事者はもう30代・40代オーバーなんですけど、その人達が、「自分の出生を隠されてきた」ていうこと自体が問題で、そういう法律が、ちゃんとできたらいいなって思ってます。
ただ今回の法案は簡単に言うと「ドナーの気持ちが変わってしまったら知ることができなくなってしまう」ようなもので、じゃあそれってなんの為に作るの?全然それは知る権利ではないと、その人達も反対していました。
更に第三者の卵子・精子提供を受けての不妊治療を、法的婚姻関係にある人のみに制限する内容だったので、私たちは反対の声をあげていました。属性じゃなくて「その人自身が親になる準備ができてるかどうか」で見てほしいと思います。
salad:SNSなどで個人間での精子提供などを多数見つけることがあります。こういった現状を見てしまうと、やはり、精子提供や代理母出産などは、法律で整備すべきことだと思うのですが、当事者としてはどうお考えでしょうか?
今回の法案は「未婚の女性が、海外の精子バンクや兄弟など第三者からの提供を医療機関を通じて受けることを禁止する」もので、そもそも個人間での提供は制限されないんですね。
「何百人にも提供してました…みたいな問題のある精子提供ドナーの人達は、全く取り締まれない」と、伝えられています。
個人間で提供している第三者が誰なのか、その人が、どういう気持ちで、どういう想いでやってるのか…ということまで、ちゃんと関わってくれるのであれば、凄くいいなとは思うんですが、実際はそうはなっていないです。
「精子バンク」という、ルーツもわかっていて、感染症などが防げるように管理されているところは凄く制限されるのに、そうじゃない個人間での提供は認められるという内容なのです。
そうするとどんどん無法地帯に、グレーになっていく、水面下での取り引きになってしまうことを加速させてしまうことに、1番問題を感じています。
なので、「やるならちゃんとやってほしい」っていうところではありますね。
代理母出産に関しても全く話にも出ていないので、政治家たちは、全くそこは進めようという気もないし、進むようなところもないと思います。私も進んでほしいかって言われたら…個人的には簡単に話せることじゃないし、もっと色んな人達と議論をしていくべきことだなと思っています。
どんはれ:伝統的な家族形態では、少子化をくい止めることができないように感じました。養子縁組や、同性婚など、どんな法整備があれば、子どもたちは生きやすくなるでしょうか?
難しいですね。子供達の「生きやすさ」でいうと、家族の多様性は既に普通にあることなので、もっと世の中に伝わればいいなと思います。
「生きやすさ」の部分だけ言うと、今は貧困だったりとか、親が仕事して子供の行き場がなかったりする問題もあります。
一方で、映画の中でも政治家が同性カップルは子どもが産めない、生産性がない……という差別発言をしたことについて取り上げましたが、かといって「同性愛カップルも子供を作ってるんですよ。だから少子化に貢献します」って訴えるのは、すごく嫌なんですよ。
産む産まないも自由というか個人の権利が尊重されるべきだけど、そこに選択肢がないわけじゃないですか、子供を持ちづらいというか…そこに圧力があること自体どうかなって思っています。
法律で制限されますとか言われると「正しい家族じゃないと子供は持てないのか」「産みたい人が産めない社会」ってなんだろうって感じます。
「同性愛者ばっかり増えたら子供がいなくなりますよ」「いや、いますよ」という同じレベルで議論をしたくない。
そもそも「少子化」というもの自体の問題も、また別にあるんじゃないかなって思います。
Pink:友人に不妊治療で長年大変な思いをしてる女性がいるので、年齢の問題や保険適用問題などをわかっていたつもりでしたが、同性カップルは保険適用対象外と知って、多様性の時代に反しているのではないかと思いました。法改正が進むことで、どのようなメリット、いい影響が出ると思いますか?
「第三者の提供」の場合は、男女夫婦も保険には適用されてない状態なんですね。
だから、同性カップルの保険適用っていうものは、夢のまた夢というか、映画に出てきてた不妊治療中のカップルも、「やっぱりお金の問題が大きい」とは、言っていました。
同性カップルが精子バンクなどの第三者の精子を用いて不妊治療を受けたいと思っても、受け入れてくださる病院というのは、本当に日本に片手に納まるぐらいしかありません。
保険なんか夢のまた夢なので、皆さん「多分、保険適用の対象になることはほぼ無いんじゃないかな」って、思いながら何百万も払っているような状況です。
現時点では、限られた人しか精子バンクは利用できないので、ネットにいる精子ドナーだったりとか、兄弟、パートナーの兄弟にお願いしたりして、病院を介さない方法で精子提供を受けることをされてる方がかなり多いです。
今回は映画の中には登場しないのですが、結構そういう形で行っている方が多いですね。ただそれは自己責任になってしまいますし、個人での取り引きというか、水面下で行われているので、分からないところはあります。

迫るタイムリミットや自身の卵子の数、高額な費用で悩むカップルの姿も描かれていました。©一般社団法人こどまっぷ
どんはれ:同性カップルへの偏見は海外より日本の方が強いのでしょうか?
同性カップルへの偏見は海外の場所にもよりますけど…国によっては宗教的な部分でタブー視されていたり、法的に強く弾圧されている場所など、色々なケースがあります。
日本は「見て見ぬふりをする」というか「知ろうとしたくない」というか「こっそり知りたい」というか、そういう傾向を感じます。
みんな差別に対して差別意識があるというか、「差別という言葉を使っちゃいけない」って、どっかで思っていたりすると思うので、そういう意味では「見えない差別」「マイクロアグレッション(無意識の差別)」が強いと感じられます。
島川:壁を感じたりすることもありますか?
ありますね…でもそれは多分私自身も、知らない属性、知らないマイノリティーの方に対して壁をどこか作ってるように、知らないから、分からないから。
「傷つけたくない」「怖い」など色々気持ちはあると思うんですけれども、やっぱり「これ聞いちゃいけないだろうな」「これ言っちゃいけないだろうな」て、知らないと皆さんあるじゃないですか。
だから壁は当然感じる時はありますし、私自身も人に対して壁を作ります。
いけないなって思うんですけどね…そこから当事者が歩み寄るのか、他の人がそれでも声をかけてくれるのかで、少しずつ壁が低くなっていくのかなと思いますね。
どんはれ:同性の親を持つ子どもへの差別や偏見もあるかもしれませんが、もしいじめにあったときどう対応したいですか?
それが「親が誰なのか」によっていじめがあるのかどうかというところも大きいかなと思います。
私は学生時代ずっといじめられてた人間で、結構酷いいじめがありましたが、私の親はいわゆる男女の普通の考え方の家庭で、家族のことでいじめられたことはありませんでした。
私達のことで何か嫌なことがあったら、絶対に戦おうと思いますが、そこで一番守らなければいけないのは、子供の心だと思っています。
「大好きだよ」「大切だよ」っていう愛の部分は伝えてますし、「なぜ生まれたのか?」というところは、どこまでも向き合いたいとは思ってます。
子どもが向き合いたくないと思うのであれば、それも受け入れて、私たちは向き合おうと思います。それはもうずっと…最初から、生まれる前から考えていたことなので。
カミングアウトについて

©一般社団法人こどまっぷ
Pink:LGBTQについて、以前よりは周囲への理解が深まったのではないかとも思うのですが、親へカミングアウトできたとしても、会社などへの理解はさらにハードルが高いと思います。カミングアウトすることについて、どのようにお考えでしょうか?
私はカミングアウトした方が楽になるパターンと、楽にならないパターン、どちらの例も見ているので、自由と言うか、したくない人は、しなくていいと思っています。
ただどうしても家族を作るうえで、会社の理解というのが必要になります。
ちゃんと会社や周囲の人、家族、隣人にも協力を得ない限りは、産んだ人も、産んでない方も、結構孤立してしまうというか、大変だなというのは、色んな人にヒアリングや面談をさせてもらって活動する中で感じております。
特に産んでない方が会社に全く話せていないと、育休が取れないのはもちろんのこと、「家に帰ったら赤ちゃんがいる」状態を想定せずに、残業や出張などを任されてしまい、産んだ方に育児の負担が偏ってしまう状況になってしまうんです。
そうすると2人の関係にもヒビが入りやすくなります。
カミングアウトすることとして、まず自分が、「同性カップルである」ということがひとつ、もう1つは「子供がいる」ということがひとつ。
会社に対してできる人はカミングアウトしていますが、皆さん子供を「産む」「育てる」ってなった時に、「カミングアウトせざるを得ない」というのが現状かなって思います。
外資系でなければ、日本の企業は、そういうパートナーシップ制度とかファミリーシップ制度をしっかり導入してる会社は、凄く少ないです。
会社に理解がないというより、そもそも困っている人たちがいることが見えていない所もあると思います。
まずカミングアウトするところから始めないと次が進まない、ファーストペンギンにならざるを得ないことに皆さん凄く苦労されてます。
Pink:私の親も含めて、世代によって同性カップルを受け入れられない人たちがいることは厳しい現実だと思うのですが、どのようにしたらもっと理解を得られると思いますか?
「カミングアウト」っていう文化自体が、海外の文化だなって感じていて、私はそれを「カミングイン」って言ってるんですけれども、「知った上でインしてもらった方が受け入れられる人達が多いんじゃないかな」と思っています。
いきなり「あなたと私は違います」って、パンッてやられてしまうと、皆さん「おおっ!」ってびっくりされてしまいますので。
私自身、親に同性カップルを理解してもらえなくて、最初に私のパートナーを連れて行った時に、冷たく接さられてしまいました。その時に当事者の1人として、受け入れてもらうためにやっていったのは、「人」を知ってもらうっていう努力をするということです。
人権とか、セクシュアリティの知識があった世代ではないので、「人」として知ってもらうってところを重視しました。
その人の属性が何かというよりは、その人自身と出会って会話をしてもらって、その人を知ってもらって、好きになってもらって、「人として受け入れてもらう」。
それからその人のセクシュアリティを知ったら、多少動揺はするかもしれないけれども、もう「嫌いになりきれない」って感じてくれるのでは無いかと思います。
私達は一軒家に女性同士で2人で暮らしていて、更に子供が出てきて、更にシェアメイトで外国人の女性が1人住んでいるので、「あの家一体何なんだろう」って近所からは思われていると思います。
受け入れてもらうのに必要なことは「挨拶をきちんとして」「ゴミ出しを綺麗にして」…こういう日常の繰り返しで受け入れてもらうことだと思います。
最近は隣のおじさんが、うちの子供と同じ世代ぐらいの孫が外で花火している時、「ちょっとおいで」って花火に入れてくれたりとかして、そういうことで繋がっていくと感じています。
その人達には、別に自分たちのセクシュアリティはカミングアウトはしてないですけども、なんとなく気付いてくれたらいいな、でも言ったら嫌われちゃうかな、みたいな感じです。
カミングアウトした時に嫌われないためには、社会に色んな人達がいるっていうことを、「世の中が周知してる」っていうことは、本当に大きいのかなと思うので、そういう活動も必要なのかなって思っています。
これまでのこどまっぷでの活動についてや、活動への想い

©一般社団法人こどまっぷ
salad:今回は、精子ドナーから生まれた子供たちやそのカップルが主でしたが、こどまっぷ様の会員の中には、代理母出産などで生まれた家族などはいらっしゃいますか?
うちの団体では、会員の方ではいないと思いますし、問い合わせ自体があんまりないですね。
たまに情報提供を求めて来る方はいらっしゃるんですけれども、「エージェントを挟まないで、繋がりのあるアメリカの病院の先生に直接聞いてください」とお伝えをしています。
りんごいくら:私は白血病を罹患し骨髄移植前に、未受精卵子凍結保存を11個したことがあり、その後2回再発したので29歳で保存を停止しました。その後、不妊で悩むカップルに未受精卵子を提供したいと専門クリニックに依頼したことがあります。
これまで会員の方で、卵子提供を利用したカップルはいらっしゃいましたか??
「こどまっぷ」では女性の「第三者の精子提供によって出産する」ということを望んでいる方たちが凄く多いです。
属性としてはトランスジェンダー男性、FTX、女性同士カップル、もしくはシングル女性の方が多いですが、自己卵子で妊活してるっていう人達が、私達の周りには多いなという印象です。
他の団体だと、卵子提供を望んでる方とか、代理母(サロガシー)の家族もステップファミリーもみんな一緒になっているところがあります。
今、卵子提供が日本では難しさがあるので、受診された専門の病院がすんなり「提供しますよ」と言ってくださったのかや、りんごいくらさんの卵子を今後どうするのかって話になったのか分からないのですが、実際はなかなか表向きに声をあげられないだけで、不妊治療をしてる人の中で本当は、卵子提供を受けたい、あったらいいなという声もあるんだと思います。
ストレートの婚姻夫婦の方でも、卵子提供を望んでる人達はたくさんいるなっていうのが、私は実感しています。
どんはれ:血のつながり、自分の祖先を知ることは重要だとは思いますが、血のつながりだけではない家族の形態もあるのだなと思います。家族とはどんなものと定義しますか?
私自身「家族って何だろう」ていうのをずっと考えていて、家族っていうものが何なのか知りたくて、色んな人とそういうイベントを開いたり、それで「こどまっぷ」の活動もしている部分もあります。
私自身が自分が育った家族の中で「ただ血だけで繋がって集まっている集合体だな」って感じていて…、新しく自分が作る家族っていうものも長らく見えずにいました。
「家族の定義」というものが自分の中で変化し続けているんですが、最近は「努力して一時的にこの場所に集まっている人達」というか、努力があったり、お互いに相互理解しようとしたりする過程というか「変わっていくもの」かなと感じています。
「変わらない」という考えもあると思うんですけど、私は変化があって、お互いに配慮ができる場所であればいいなと思っています。
あと、子供にとっての「安全地帯」でいたいです。
「生まれた家族」っていうのは、「血の繋がり」のことを指すことも多いと思いますが、私の家族という定義に、血は関係ないかもしれません。
コロコロ変わるんですが、それでいいかなって…家族っていうものを定義するってよりは、「家族みたいなもの」という感じで、揺らぐものだって思いたい。
少し揺らいで、少しずつ変化して、一緒に成長していけて、見守れたらいい場所だな、という気持ちでいます。
今後の活動予定や、メッセージ

精子提供した男性とカップルが並んでお参りする一幕も©一般社団法人こどまっぷ
Pink:私は未婚で子どもがいないため、映画を観て難しく感じることも多かったので、もっと知りたいと思うと同時に、色々な家族の在り方があってもいいのではないかと思いました。もし差し支えなければ、今後の活動予定があれば教えて頂けますでしょうか?
オープンで誰でもウィルカムの、年に1度のファミリーピクニックっていうのがあります。いつも春先にやってるんですが、大体100人ぐらいの色んな方達がいらっしゃるので、もしよかったらXとかこどまっぷを見ていただいたら情報がありますので、ファミリーピクニックの際にはぜひ来ていただけたらと思います。
それ以外は当事者の集まりとか、そういうのが凄く多いですね。
なかなか皆さんに来てくださいって言えなくて申し訳ありません。
ぜひファミリーピクニックでお会い出来たら嬉しいです。
島川:これを読んでいる同性カップルの方や、映画を観てくれた方に、伝えたいことはございますか?
映画を見てくださった方に伝えたいのは、この映画の家族って、本当に「特別ではなく、普通に隣にいるかもしれない家族です」ということです。
この映画をきっかけに、多様な家族の姿を、もっと社会に伝えていきたいですし、「家族ってなんだろう」と、一緒に考えることができたら嬉しいなと思っています。
「多様性とは何か」とか「家族とは何か」など考えさせられることはありますけれど、本当に誰かのためじゃなくて、社会全体に自由や安心を広げるものだなっていうことです。
未来の子供達が「自分の家族は社会に歓迎されている」と、胸を張って言えるような環境を残すために、医療や法律の領域で整備を求めるなど、活動を続けていきたいと思ってます。
インタビューを終えて
salad:とても考えさせられる内容の映画で、「家族ってなんだろう?」「子どもって何ろう?」と、自分自身が目を背けていた部分に触れられ、再認識することができました。
私も「パンセクシュアル」ということで、女性と付き合ったことも、真ん中の方と付き合ったこともあるという、宙ぶらりんな感じです。
その中で「子供を持つ」ということも、考えたことがあるんですけど、その時はまだ若かったので、行動に移すことまでは出来ませんでした。
それに関しては後悔してないですけど、やっぱり「家族を持つ」というのは、凄く素敵なことだなと、今日改めて感じました。ありがとうございました。
りんごいくら:映画を見て、島国日本の政府や私も、閉じてばかりではなく、もっと多様性のある人々や生き方を受け入れようよ!それができたらLGBTQや同性カップルも伸び伸びと生きる方々が増えるでしょう、と願う気持ちが出てきました。
たくさんのお話を聞かせていただき、今回の「ふたりのまま」は、ず〜っと残ってほしいなって思いました。
広報のアーヤさんもおっしゃっておりましたが、公民館や学習センター、産婦人科などでこの映画を流してもらったら、「こういう新しい形で生まれた赤ちゃんもいるんだな」と分かってもらえて、自然と「多様性の広がる社会」になるんじゃないかなと思いました。 長村さん、本日はありがとうございました。
Pink:映画を拝見させて頂きありがとうございます。
初めに思ったことは、LGBTQの現状のその先を観ることができたということです。
私自身、結局子供を産まないまま、今に至るのですが、あの映画を見る中で、子供の存在が凄く大きいなと感じ、親に孫の顔を見せたいなと凄く思いました。
同性カップルの話はよく聞きますし、周りにも、知り合いにもいて、みんなそれぞれ悩みが多くありますので、そういう人達のためにも今回の映画がたくさんの方に見ていただけることにつながればと思います。
どんはれ:「個人の幸せ」と「社会の幸せ」は、連動しなければいけないと思うんですよね。
「同性カップルは生産性がない」と政治家の人に言われてしまって、私は「生産性がない」というのがよく分からないですが、「子供が欲しい」と思う感情は自然なものなので、異性カップルであっても同性カップルであっても、子供が欲しい育てたいと思う人が、育てられる社会になっていった方が少子化も食い止められると思いますし、多様性が受け入れられる社会が、個人の幸せにも繋がるのではないかなと思いました。
あと映画を見て、お子さんのおむつを替えたり、歯を磨いてあげたりする様子を見てどこの家庭でも、同性愛カップルでも異性愛カップルでも、「徐々に家族になっていく」という感じが、とても優しい気持ちになれて、よかったと思いました。本日は、インタビューありがとうございました。
島川:私はこの中では唯一の男性なので、男性目線でお伝えしたいと思います。
映画を拝見していて、精子を提供してくださったデイビットさんが凄く印象的で、そもそも凄く理解があって、提供先のご家族とも仲良くされていて、「助けになりたい」という意思で活動をされている方なのだなと感じ、こういう方に精子を提供してもらえたらありがたいなと思いました。
私は全然知識がなかったのですが、こういう方もいらっしゃることを知って、みんなが理解を深めると、皆さんがもっと生きやすくなるのかなと思いました。
ぜひ今後ともメディアを通して、お手伝いさせていただけたらと思います。
アーヤさん:他のメディアさんで、あまり聞かれたことがなかった、色んな角度、視点からのご質問もいただいたりしたので、こういう視点からも問いを持っていただけるテーマの映画なんだなっていうのを気付かせていただきました。ありがとうございました。
長村監督:同じ気持ちです。
映画の上映に関するインフォメーション
映画『ふたりのまま』広報のアーヤさんによると、「ここから福岡も含め、ぜひ劇場公開が色々な地域に広がっていったら嬉しい」また、「映画館だけじゃなくて、公民館、カフェ、企業など、色々な所での上映の場っていうものが広がってきているので、この映画も草の根的に広げていきたい」とのことです。
こちらの映画が全国に公開が広がっていってもらうためにも、映画を見た皆さんや、興味を持ってくださった皆さんの声が必要です。
2026年1月以降は上映会の受付も以下のフォームで開始される予定です。
▼予告映像
前編はこちら
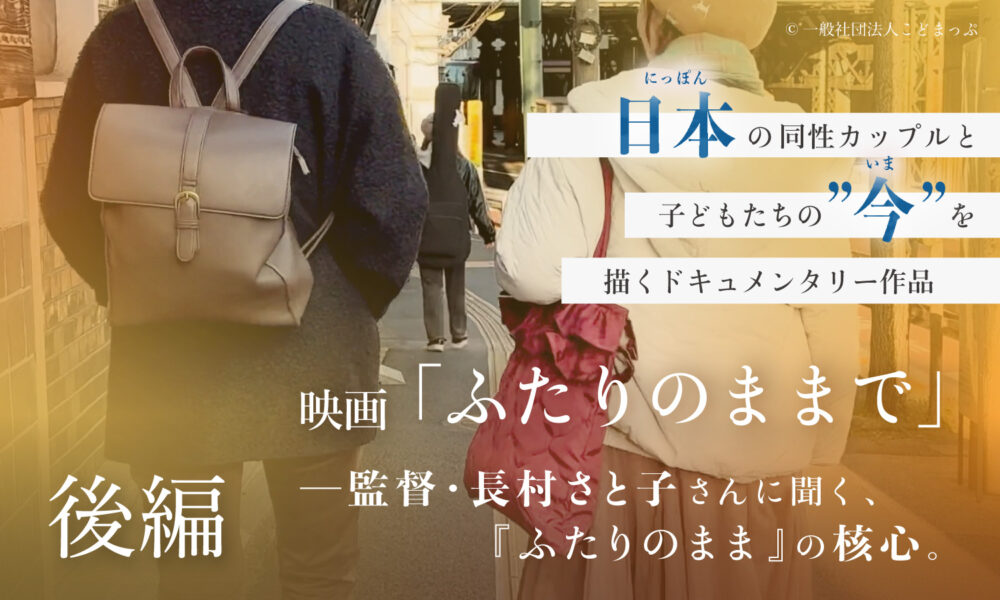
















コメントを残す