この記事は約 8 分で読むことができます。
図書館のイメージ
こんにちは、そして、お久しぶりです、hibikiです。
皆さんは、「図書館司書」という職業にどんなイメージを持ってますか?
私が知る限り、かなりの女性の方の、憧れの職業だと言ってもいいかもしれませんね。
実際に、TANOSHIKAに入所してから、以前していたと話すと、羨ましがられる事が多かったです。
一般的なイメージは、静かな空間、たくさんの本、静かな音楽。
そして、椅子に座って優雅に仕事をしている図書館司書。というイメージでは、ないでしょうか?
否、それは、はっきり宣言いたします。外見だけです!!
図書館の仕事を知ってもらって、私や現在、図書館で働いている司書さんたちの仕事ぶりを、憧れでなくて、実際に感じていただきたいなと思い、昔の自分と向き合うつもりで、原稿を書かせていただきました。
久しぶりに記事を書いてますので、支離滅裂な文章だったらどうしようかと、ドキドキしながら執筆しております。ぜひ最後までお付き合いください。
図書館の仕事は優雅
さてさて、外見だけというのがどういうことかといいますと…図書館の裏側では、職員がみんなあくせくと動き回り、電話やら書類におわれ、新刊のデータ入力、新聞、雑誌などのことで、優雅に働くなんてことは、決してありえません!(断言)
それぞれの担当がいて、その担当の仕事をします。
私が最初に就職した図書館の種類は「公共図書館」いわゆる「市立図書館」でしたが、図書館の中でもおそらく、一番大変だと思います。
市民の税金で、本を購入するので問題が一番発生しやすいと私個人は、今でもそう思っています。
今日も、図書館は走るよ!
私が初めての担当になったお仕事は、「動く図書館」別名=移動図書館車です。
英語で「BOOK MOBILE」(ブック・モービル)
通称BMです。
名前のとおり、大きなキャンピングカーのようなサイズの車に、約2500冊~3000冊、本・雑誌・新聞を乗せて、毎日、月~金曜日に、決まったコースを走ります。
雨の日、雪の日(よっぽどの悪天候)でも、そのコース通りに、目的地へと向かいます。
午前中2件、午後3件は回っていたと思います。
ブックモービルは、だいたいは、図書館が遠い方などのためにあり、
目的地は、公園、小中学校、老人ホーム、公民館など。多岐にわたります。
また、市区町村によっても、違いますので、利用されたい方は、図書館のHPや問い合わせしてください。
ちなみに、久留米市にもあります。
ここでの司書のお仕事についてです。
コースによって借りられる本の種類を用意します。
これが、最初はすごく大変な作業です。
スケジュールは毎週だいたい一緒でも、借りられる本の種別が、毎回違うのです。
公園での利用者は小さい赤ちゃんや、子供さんを連れた若奥様方ですが、行くたびにほしい本をリクエストされるのですが、これ、かなり難しい作業です。
小さい子どもといっても、1歳から5歳ぐらいの子供たち。
ここでも、司書の『本の選別』の力が試されます。
「子供だから絵本でいいんじゃない?」って言っていた実習生も、簡単と思っていたけれど、前半でかなり息切れしていました。
小さい子供のパワーは、半端ではありません(笑)
子供相手が一番、体力もっていかれます。可愛いですけどね。
BMの利用者さんたち
BMは常連さんが、結構いらっしゃってくれるし、ご新規さんもいたりして、名前は知らなくても自然と壁がなく、本音で話すことができるのです。
何より、その場所に来て頂くのが楽しみなので、館内で仕事するより私は楽しかったです!
貴重な意見が、気軽に聞けたりするわけですが、図書館内だと、静かにしなければならないので、こうはいきません。
今のほしい本、そこの地域ではやっている本様々な情報が手に入り、参考になります。
館内でも、「リクエスト用紙」というのがありますが、それを口頭でリクエストを受けます。
そして、それをまた二週間後に図書館用語で「選書」して、備えます。
その繰り返しです。
私が苦戦した「選書」
よく私の司書の友人と、「選書」が一番難しいよねというお話をします。
「選書」は司書の基礎的な基礎の部分。
学校で、多少学びましたが、そこは十人十色です。
ある日、いつものコースに入っている老人ホームに行くと、とても上品なご年配の女性から「時代劇の本が読みたい。何かおすすめはないかしら?」と尋ねられました。
こういう質問は、司書にとって当たり前に聞かれますが、私は入社したばっかりだったので、かなり苦戦しました。
市立図書館というのは、基本、そこの市町村に住んでおられる方がメインで来られます。
新人とはいえ、利用者の方はそれをご存じありません。
人並みの図書館職員として、リクエストされます。
一口に「時代劇」といっても、たくさんの種類があります。
皆さんから見れば簡単に思うかもしれませんが、司書はその中身を考えます。
男性・女性向き、その方の好み、利用者の感性、どの時代なのか、作家の選別等。
(今考えると、頭から煙が出ます)
時代劇だとかなり偏りがあるということが、分かりました。
私は、当時、二十歳代でしたので、ヤングアダルト(10代向けの小説)、漫画、他推理小説をしか読んでなかったので、先輩たちのお力をお借りしたこともあります。なんやかんや調べて、準備を進めました。
いざ、本を持って!
実際に、「時代劇」の本は、結構、種類が豊富。
そこから、選んだのは「江戸時代」の小説。女性向けです。
ここの図書館は、私が勤務していたころは、貸出冊数は、一人5冊まで。期間は、二週間です。
とりあえず、5冊以上は持っていきました。そしてなるべく文庫で。
お年を召した方には、普通のサイズの本だと重いかなというのを配慮しました。
その方の好みに合うあうか、借りてもらえるかが不安でしたが、
その女性は、本を持っていくと、意外にも大喜び!
かなり、どれを借りるか悩んでくれました。
そして、基本そこから2~3冊借りていかれました。
ちなみに、記憶に残っているのは、やはり女性作家さんの「時代小説」でした。
試しにご紹介しますと、『平岩弓枝さん』『三浦綾子さん』『永井路子さん』等。
他にも、宮部みゆきさんやら、紹介した本はほとんど借りて行かれました。
そして、いつも行くと「おもしろかったわ、また、あなたのおすすめの本が読みたいわ」と言われ、ご指名を受けました。
それから、辞めるまでその方の「時代劇」の本を、二週間ずつ『選書』して、毎回喜んだ顔でお礼を言われるという日が続きました。それがきっかけで私も、「時代小説」や歴史の背景を書いた研究者たちの本を次々に読破するようになりました。
私にとってのBM(移動図書館車)とは
今、振り替えってみると、BM(移動図書館車)は地域にとって、かなり必要なものです。
久留米のように大きな市は、あちこちに支所があります。
しかし、小さな市にとってみれば、遠方と図書館をつなぐ大事なアイテムのような気がします。
司書の仕事は、これ以外にもたくさん仕事があります。
しかし、このBMというのは、結構知らない方が多いと思います。
図書館司書に憧れていいな~といってくださる方がたに、知っておいてほしかったのも事実です。
ぜひ一度、BMについて調べてみて、気になったら一度利用していただきたいと私は思います。
司書と気楽に話せるとてもいい機会です。
他の市区町村によっては、廃止されている自治体もあるので、もったいないと感じました。
BMを通して。
よく、質問されるのは「また、図書館に戻りたいですか?」ということを聞かれます。
答えは、「NO」。「もう、十分です。」というのが、答えです。
私は、この仕事を始めてから、病気を発症しました。
もちろん、つらい時期でもありましたが、BMに乗っているときはとても楽しかったです。
夏や冬は、暑いし寒いけれど、春と秋は最高に気候がいいときは、ちょっとしたドライブ感覚です。
BMの日は、図書館内で嫌なことがあっても忘れることができました。
もしまた関わるとしたら、BMに乗って、公園のお母さん方、子供さん、ご高齢の方のために、令和のBM(移動図書館車)に乗ってみたいですね。
仕事じゃなくて、ボランティアでもいいので。
今の時期だと、最高に気持ちがいいだろうな~と思います。
今回の記事を通じて図書館の仕事を少し知ってもらって、私や現在、図書館で働いている司書さんたちの仕事ぶりを、憧れでなくて、実際に感じていただけたら嬉しいです。
私事にお付き合いいただきありがとうございます!!
また、いろんな図書館の謎な部分の記事を書いていけたらと思ってます!
→HOME
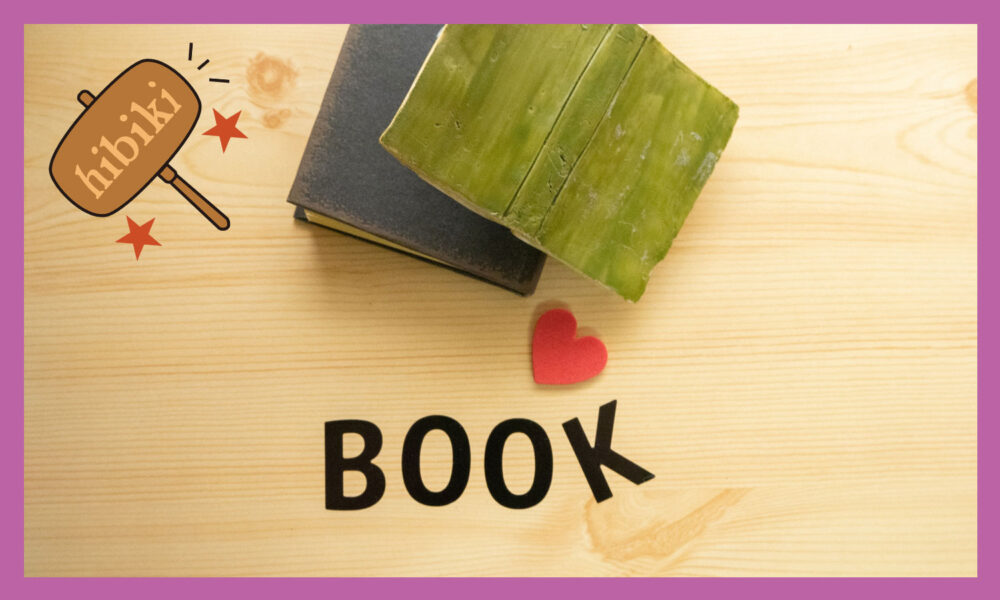












私も昔移動図書館、BMの仕事をしていました。週3回一日2カ所回りました。だいたいは公園を利用してステーションとしていましたね。本を借りに来る親子さんや年配の方々の楽しそうな顔が今も目に浮かびます。本の選定や整備も楽しかったですよ。
くにさん
コメントありがとうございます。楽しいですよね~。
図書館に一日いて、館内で仕事するより外に出て様々な方とお話するのが、かなり
仕事の情報に役立つので、勉強になります。
外なので図書館のように静かにしなくてもいいので、大声出して話してました。
それが、また新鮮。
選書も、準備も楽しんでやってました。この記事に、反応してくださりありがとございます。