この記事は約 4 分で読むことができます。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
今では、女装をする男性は、多くいます。最近の男性は、美容もしますし、脱毛したり、日傘も差しています。
私の子ども時代と違い、美への意識が高い男性が、多くいます。
女性が男性の格好をする様に、男性が女性の格好をする様な現代の中で、パッと見では、性別がどちらなのか分からないほど、男女間の性差がない状態ですよね?
そんな異性装を記録した、展示会が、2022年に開催されていたことを、皆さんは、ご存知でしたでしょうかー?
日本の文化の中でずっと育まれ、色んな美術作品や資料で記録されてきた【異性装】では、2022年、古代から現代まで、その系譜を辿り着く画期的な『装いの力―異性装の日本史』展が、東京都にある渋谷区立松濤美術館で開催されていました。
『装いの力―異性装の日本史』展は2022年10月30日まで。祝日を除いた月曜と9月20日、10月11日は休館日でした。
今回は、2022年に開催された『装いの力―異性装の日本史』展では、どんな資料が掲載されていた?などを紹介したいと思います。
日本の異性装を記録した『装いの力―異性装の日本史』展、その全貌とは?

画像引用・参考:「装いの力―異性装の日本史」展|渋谷区立松濤美術館
日本で異性装に言及した最古のケースは、ヤマトタケルが女装で敵の隙を突くという古事記のエピソードまで遡ります。平安後期の作品と想定されている「とりかへばや物語」では兄妹が立場と装いを替え玉し、室町期の「新蔵人物語絵巻」の作品の中では男だと言い放って、参内した娘が帝の寵愛を受けて出産しています。
江戸時代の絵巻は、彼らの装いは本人のアイデンティティーや性的指向と関係なく、立場や職業によって要求された異性装でした。
白拍子や能など芸能の世界でも、異性装のケースは数え切れないほどあります。桃山時代の「阿国(おくに)歌舞伎草紙」のケースでは、男装でかぶき者を演じた出雲阿国(いずものおくに)が女装の男性と共演する様子が描かれています。
阿国歌舞伎は少年による若衆歌舞伎、男装の遊女などによる女歌舞伎などに展開しています。阿国歌舞伎が風俗をかき回すという理由で禁止に至ると、あらすじに重きを置いた、成人男性だけで演技をする野郎歌舞伎が誕生し、現代の歌舞伎の原型の発展となりました。
歌舞伎の人気役者を描いた読み物や錦絵、祭典でお披露目するイベントというフィクションの世界では、異性装の登場人物たちが大衆を大いに楽しませました。実社会では、身分の高い男性の女装には寛容だった反面、男装した女性は罰を受けたという非対称性がありましたが、異性装という選択肢は緩やかに受け入れられていました。
参考:ヤマトタケルも?異性装の日本史 美術作品で系譜たどる展覧会=訂正・おわびあり 朝日新聞デジタル(2022年)
後日談
『装いの力―異性装の日本史』展の最後の展示エリアでは、1989年から関西で続くドラァグクイーン・パーティー「DIAMONDS ARE FOREVER」のメンバーがブランディングしたインスタレーションが展示されています。
一般的なドラァグクイーンは、女装したゲイの男性のパフォーマーであることが多いといいますが、女性クイーンも出演するDIAMONDSを率いる方は、「異性装をしているという意識は全くないですね」と話し、「度を超過しながら、どれほど、世間の常識から逸脱するだけが極めて重要な観点ですね」と説明しました。
44性別越境の歴史に詳しい明治大学非常勤講師の三橋順子さんは、
「偶然性別を越えているというポイントでは『異性装』ですが、二次元的に性の境を越える『越境』ではなく、時間や空間など多くの境界を越えていく『超越』的なものを、DIAMONDSなどは表現したのではないでしょうか?」
と説明しました。
noteでも書いています。よければ読んでください。
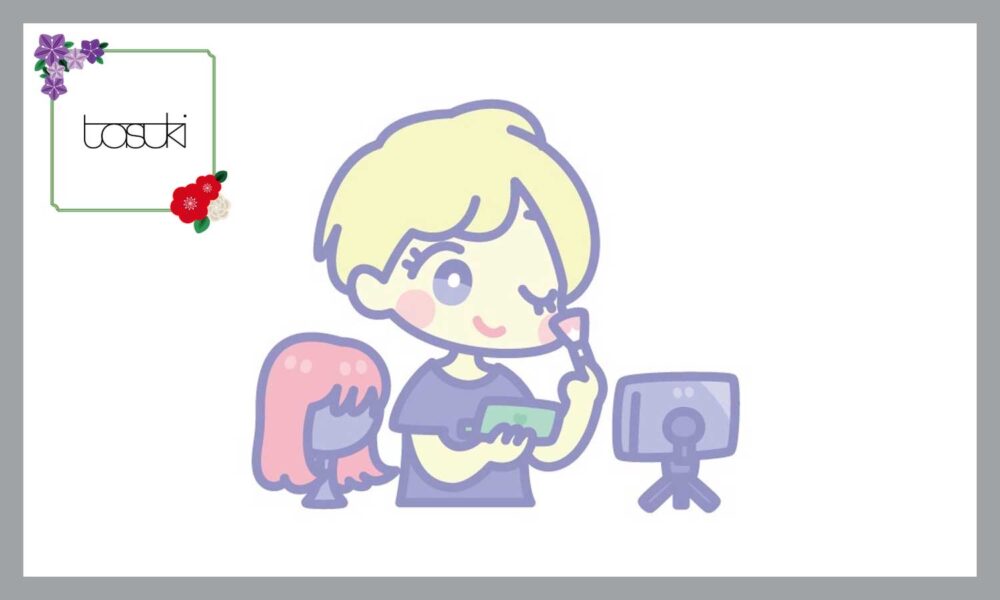




















コメントを残す