この記事は約 13 分で読むことができます。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
川崎病(Kawasaki disease)とは、1961年に川崎富作博士が最初の患者と遭遇し、1967年に50例を総括した論文を発表したことでその歴史が始まった、原因不明の病気です。
手足の指先から皮膚がむけていく症状を伴う子どもの「急性熱性皮膚粘膜りんぱ腺症候群」として発表された症候群が、実は新しい病気であると判明し、博士の名前を冠して川崎病という病名になりました。
川崎病を発症する原因では、ウイルスの感染、細菌の感染、何らかの環境物質による刺激などが想定されていますが、現在もなおその原因は特定されていません。ですが、川崎病を発症する確率は日本人など東アジア系の人種で多い傾向です。
1970年以降は、ほぼ2年毎に川崎病全国調査が実施されています。1979年、1982年、1986年に全国的な川崎病の大流行が認められた後は、毎年患者数は5,000人前後で推移していましたが、1990年代後半から年々増加傾向で、2005年に川崎病の年間患者数が1万人を突破し、その後も増加の一途を辿っています。
川崎病は小さな赤ちゃんが主に罹患する疾患であり、全ての患者さんの中で3歳未満が66.2%、5歳未満が88.2%を占め、罹患率のピークは乳児後半(6~11ヵ月)です。
患者さんは、若干男の子の方が発症しやすく、全国の実態調査の結果では毎年およそ15,000人の子どもが川崎病を発症しています。ある研究では、そのピークが、男の子が月齢6~8ヵ月、女の子は月齢9~11ヵ月というデータがあります。
川崎病は遺伝する病気ではありませんが、親子例は約1%、兄弟例は1~2%程度みられています。
川崎病はヒトからヒトへと移る病気ではありません。そのことで予防方法はありません。早期に川崎病の治療をすることが必要です。
今回は川崎病の症状、合併症、診断基準、治療法などについて、特集します。
▽症状

①5日以上続く発熱(ですが治療を施したことによる5日未満で解熱した場合も含みます。抗菌剤は無効で、通常の解熱薬は効きづらく、発症した子どもが不機嫌な場合が多い)
②眼球結膜充血→両方の白目の部分が赤くなります。病初期から見受けられ、4から5日間続きます。目やには出ません。
③口唇の紅潮と、乾燥、ひび割れ。舌は表面にブツブツが目立つ「いちご舌」、口腔咽頭粘膜のびまん性発赤→舌や唇が赤くなります
④急性期における非化膿性頸部リンパ節腫脹→両側性の首の痛みを伴ったリンパ節が腫れます
⑤不定形発疹・BCG接種部位の発赤→身体が赤いブツブツが出ます。お腹や胸などを中心に麻疹様、蕁麻疹様、風疹様など不定の皮疹が見受けられます。普通は、水ぶくれができることはありません。また、BCG接種部位が赤くなるのが川崎病の特徴で、これは他の病気では見ることのない現象です。
⑥四肢末端の変化:(急性期)手足の硬性浮腫、掌蹠ないしは指趾先端の紅斑→足の裏や手のひらが赤くなり指先が腫れます。これは指で押しても痕が残らないため、硬性浮腫と呼ばれています。
(回復期)指先からの膜様落屑(まくようらくせつ)→1週間以後の回復期には指先と爪の移行部から皮膚の皮が剥がれ始め、完治した頃に皮がむけてきます
これらの主要な症状以外に、下記の症状や風邪症状なども、全身に拡大する小さな血管の炎症によって発症するケースがあって、川崎病の確定診断では参考となる所見です。
・心循環器系障害:心筋炎、聴診上の異常(微弱心音、心雑音、頻脈、馬調律など)、心電図異常が見受けられます。胸部X線では、心陰影拡大し、胸膜炎、心膜炎が証明されるケースもあります。心エコー上、冠動脈の拡張は川崎病の発症から5日頃から始まり15日頃が最も頻度が高く見受けられます。
・神経症状:稀に髄膜炎・意識障害・けいれんが見受けられます。
・消化器症状:腹痛・嘔吐・下痢、麻痺性イレウス・肝障害・胆嚢腫大・黄疸が見受けられることがあります。
・関節症状:一過性の関節痛が見受けられますが、明らかな関節炎は極めて稀です。
・臓器症状:膵障害、腎障害
①〜⑥の上記6主要症状のうち、4つの症状しか認められない場合でも、経過中に心血管造影法もしくは断層心エコー法で、拡大を含んだ冠状動脈瘤が確認され、それ以外の疾患が除外されれば川崎病と確定診断をします。
川崎病の診断の手引きの基準は満たさないものの、他の疾患の可能性が否定され川崎病と想定される「川崎病不全型」も15~20%前後存在します。「川崎病不全型」は決して軽症だというわけではなく、心臓系の合併症も少なくないことから、発見が遅れることなく治療を始めることが推奨されています。
▽類似した間違われやすい病気
▽川崎病の経過

画像・引用:川崎病 つちや小児科クリニック
▽合併症
川崎病の大部分は約2~3週間で症状が改善します。およそ3~10%に、心臓の筋肉に栄養や酸素を送る冠動脈(かんどうみゃく)の異常という血管に強い炎症が発生すると、血管の一部が瘤(こぶ)の様に膨らむ冠動脈瘤(かんどうみゃくりゅう)を作ってしまう場合があって、この状態に陥ると川崎病の心臓合併症だと言われています。
血管の炎症が継続すると、冠動脈の血管壁が変化が生じます。川崎病を発症して6~8日で血管壁の内部が腫れて“水ぶくれ”の様な状態を生じ、発症して8日~10日経過すると、血管を内側から支えている内弾性板が断裂してしまいます。この内弾性板が断裂すると、冠動脈は血圧上昇に耐え切れずに風船の様に膨らんでしまい、発症して10~12日後には冠動脈瘤が生じてしまいます。
この冠動脈瘤は、瘤の径が大きければ大きいほど重症と言われ、特に最大径が8mm以上となる巨大冠動脈瘤のケースでは、瘤の中に血栓が出来やすくなり、冠動脈自体を詰まらせたり狭くしたりして、心臓の筋肉に十分な血液を送ることが出来ず、虚血性の心筋障害を発症してしまうケースがあります。
冠動脈瘤が発生すると血液の流れが滞って血栓という血の塊が出来やすくなり、その血栓が冠動脈を塞いでしまうとその先の血流が途絶えて栄養や酸素が届かず、心臓の狭窄や、非常に稀ですが、心臓の筋肉が壊死して動かなくなる心筋梗塞を発症する場合があります。
そのため、冠動脈瘤を予防するためには、川崎病を発症してから、遅くとも7日以内に治療を始めることがカギとなります。
残念ながら現在でも、重症の川崎病で急性期に心臓合併症で亡くなる患者さんは、全国で毎年数名程度いるという統計結果も出ています。
▽診断基準
診断では、まず問診と診察で川崎病の症状を確認し、血液検査で炎症の程度や合併症が出ているかいないかを解析します。さらに、心エコー(超音波)検査で冠動脈や心臓の状態を検査し、心電図検査で心臓の筋肉に異常をきたしているか否かを検査します。
心エコー検査では、冠動脈瘤があるか無いかを、心臓に超音波を当てて検査します。健康な人の冠動脈の画像は細い線状をしていて、子どもだとおおよそ直径2~3mmです。その反面、冠動脈瘤を発症した川崎病の患者さんでは、冠動脈の画像がボコボコと部分的に膨らんでいます。重症化リスクが高いほど、冠動脈瘤は数も多く、大きくなることが明らかになっています。
▽治療法
❶免疫グロブリン(血液製剤):最も信頼できる川崎病の抗炎症療法です。全身の炎症を抑制する効果があります。12~24時間を要して点滴でゆっくりと投与することから、5~7日程度の入院治療が必要となります。副作用はほとんどなく安全性の高い治療法ですが、数例点滴中に血圧低下やアレルギーなどの副作用が出現する場合があります。80~90%の川崎病の患者さんは1回の投与で熱が下がりますが、2回目の免疫グロブリンの投与が必要な患者さんも中にはいます。
❷アスピリン:内服で投与していきます。熱を下げて、血管の炎症を抑制したり、血栓が出来るのを予防する効果があります。発熱し、炎症反応が高い期間は1日3回内服し、症状の改善に併せて1日1回とアスピリンの内服を減量して、退院した後も2~3ヵ月は自宅で内服を続けます。副作用として出血時に血が止まりづらくなるケースがあります。
❸ステロイド剤:主に免疫グロブリンを投与しても、熱が下がらず、症状の改善が見受けられない川崎病の患者さんへ投与します。副作用としては、細菌やウイルスに感染しやすく場合などがあります。
❹インフリキシマブ(モノクローナル抗体):川崎病急性期にTNF-αというサイトカインの数値が高く、このTNF-αを抑制する製剤です。免疫グロブリンやステロイド剤の効果が見込めないと判断した時に使用されます。特に急性期の川崎病に対して、点滴にて投与されます。
❺血漿交換:患者さんの血液をいったん身体の外に出して血漿(けっしょう)成分を入れ替え、人工透析の様な装置を使って、身体内に戻すことで炎症物質を除去する治療法です。廃棄した血漿分は、健常な人の血漿あるいはアルブミン製剤で補充します。
❻シクロスポリン:特に急性期かつ重症の川崎病の場合に投与する飲み薬です。免疫細胞の機能を抑制し、炎症を落ち着かせる効果が期待できます。
❼その他:上記❶~❻の治療で症状が改善しない時は、好中球エラスターゼ阻害剤の投与などの処置を施します。

参考サイト
〈こども〉 vol.11 川崎病について 四国こどもとおとなの医療センター
原因不明の「川崎病」 6つの症状と診断・検査、心臓の合併症を防ぐ治療 NHK 健康ch(2023年)
川崎病とは?原因、症状、治療法について解説 MYメディカルクリニック(2023年)
2024年11月、川崎病の新たな研究成果が明らかに!
小さいお子さんを主体に感染し、全身の血管に炎症が発生する川崎病は、お子さんが暑さに晒されると発症リスクが向上することが判明したと、公衆衛生学が専門の、東京科学大学大学院の那波伸敏准教授などの研究グループが明らかにしました。
気候変動の影響で、猛暑や酷暑の日は今後も増えると予想され、研究グループは「お子さんが高温環境を避けることが、川崎病の感染リスク軽減に結び付く可能性を秘めています」と説明しました。
その研究成果は2024年10月30日付で、オランダの国際環境科学誌にて発表されました。
チームは、2011年~2022年の、年間気温が高くなる5~9月間の川崎病の日本全体の規模の入院データおよそ4万8000件を分析しました。気象庁のデータと照らし合わせて、日平均気温と入院リスクの因果関係を調査しました。
その結果、日平均気温が高いほど川崎病の入院リスクが上がりました。特に、極端な暑さ(日平均気温が上位1%となる30.7度以上)にさらされると、1番リスクが低い11.3度の場合と比較しても、5日以内の入院リスクが33%増加しました。
小児科医もしている那波准教授は、
「川崎病は後遺症を予防するために早い段階の診断、治療を受けることが重要な行動となります。地球沸騰化で暑すぎる日が増えることが予想される中で、医療従事者は気温が高くなると川崎病に感染する患者さんの数が増加する可能性を踏まえて、備えておく必要性が顕になりました」
と述べました。
参考:乳幼児かかる「川崎病」 暑さで発症リスク上昇 東京科学大チーム 毎日新聞(2024年)
退院後の生活について
川崎病のほとんどの子どもは、退院する頃には普段と変わらず元気になっています。
ですが、入院前より体温が少し高めになる、唇や目がまだ赤い、足や手の関節を痛がるといった、入院前にはなかった川崎病の症状が継続する場合がありますので、退院した後も慎重に暫くは経過観察を行います。
川崎病を発症してから1ヵ月の時点で心臓超音波検査で心臓、特に冠動脈の性状や弁の逆流の有無を確認し、後遺症が出ていないかどうかを判断します。後遺症が出ていないと診断された時は、間隔を空けながらおよそ5年の経過観察を行います。後遺症がないと判断された場合は、心臓の機能に問題はなく、運動制限の必要もありません。
川崎病の心臓合併症の冠動脈瘤は、軽症で径の小さいものであるなら、1~2年の経過した後、自然に消退することがあります。ですが、中等症以上で径の大きな冠動脈瘤は、後遺症で血管に瘤が残ってしまいます。
この時には、冠動脈瘤内に血栓が出来たり、時間経過で瘤が不規則な形で修復されて血管の狭搾が進行し、血液の流れに障害をきたす事があります。そのことで、瘤内の血栓を防ぐために治療薬の継続や定期的な外来通院での経過観察が必要で、心臓カテーテル検査などの精密検査や、場合によっては冠動脈瘤への手術などが必要になるケースもあります。
その後は、半年から1年に1回、小学校に入学するまでは、定期的に心臓の検査を受けることで、日常生活や運動、学校生活などは、普段通りにすることが可能です。ですが、川崎病を再発することもあるので、発熱した時には川崎病の症状に注意して下さい。
川崎病を発症した人は、冠動脈瘤が出現していなくても、大人になってから血管が縮んだり膨らんだりする働きが少し落ちていることが実態調査で明らかとなっていて、動脈硬化を引き起こしやすいのではないか?と疑われています。
川崎病の発症で血管を痛める危険性が高いということを忘れずに、脂質や塩分を摂り過ぎない様に、健康的な食生活を送る様に意識しましょう。

noteでも書いています。よければ読んでください。
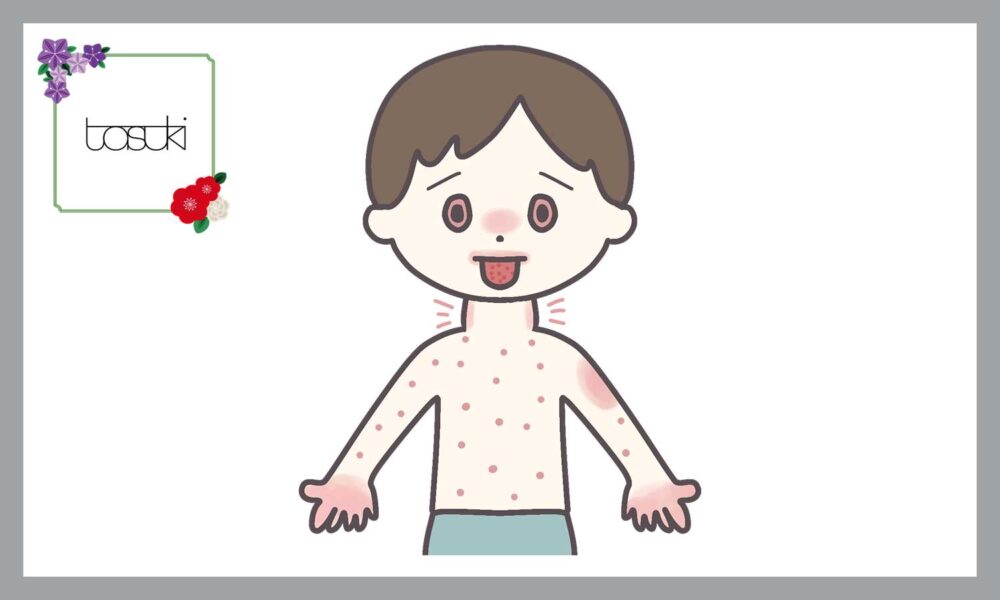



















コメントを残す