この記事は約 8 分で読むことができます。
こんにちは、翼祈(たすき)です。
私は2022年に下記の様な記事を書きました。↓
この中で、『AIスーツケース』の話を取り上げましたが、実は開発から5年以上が経過した2025年、大阪・関西万博で活用されることが決まりました!
『AIスーツケース』とは、視覚障害を抱えている人を目的地まで誘導するナビゲーションロボットで、デザインを一新した以外にも、カメラで周りの画像を認識し、建物や道路、周りの歩行者の動きに関しても音声でアナウンスするAI音声機能が搭載されています。
2025年1月、日本科学未来館やオムロンなど5者で構成する次世代移動支援技術開発コンソーシアムは、自律型ナビゲーションロボット『AIスーツケース』の新型を公開しました。
2025年4月に開幕する「2025年日本国際博覧会」(大阪・関西万博)で実証実験を実施します。
今回は、『AIスーツケース』が大阪・関西万博で実証実験が行われるまでの経緯を時系列で発信したいと思います。
2020年、
画像・動画引用・参考:AIスーツケースについて 日本科学未来館
『AIスーツケース』の開発に携わるのは日本科学未来館(東京)館長の浅川智恵子さんです。「『AIスーツケース』の普及には、社会の理解を得ることが欠かせません」と指摘し、2025年に開催される大阪・関西万博での実証実験が試金石になると感じています。
浅川さんは小学生の時にプールで目を負傷し、14歳で失明し、全盲になりました。視力を失って辛かったことは、「単独での移動」と「一人で本を読むこと」の2つを挙げました。
苦学してプログラミングを勉強し、1985年に日本IBM東京基礎研究所に入社した後、情報アクセシビリティー(利用しやすさ)を研究し、ホームページの音声読み上げソフトなどを開発しました。
2014年にアメリカの大学の客員教授に就任し、日米を行き来する様になると、空港で出発便のゲート変更などが起きた度に移動経路が分からなくなりました。そんな時、「スーツケースが案内してくれたらいいのに」との考えが頭を浮かびました。
「白杖を用いて外を行けるのは職場や学校など限定的な場所です。一人で自由に安全に街歩きを楽しむことは現在もできていません。知り合いが向こうから来ている、周囲にどういう店があって、美味しそうな食べ物があるなど皆さんが自然に得られている視覚情報を私は得られていません。この問題を解決し、周りの情報を自然に得られる様にしたいです」
と、ふと浮かんだひらめきでしたが、理にかなっていました。頑丈なスーツケースを先行させて安心を確保します。街中でも自然で目立ちません。「目の代わりとなって一人歩きをサポートしてくれます」と直感し、2017年から研究を始めました。
今後、2020年から2022年の3年の計画で実証実験や技術開発を実施し、社会実装の構想を練っていくといいます。現状では実装化の目標年はまだ決定していません。ロボットの低電力化や小型化を進めていきつつ、最初に10kg前後の重量を目指し軽量化を進めていきます。
参考:「AIスーツケース」が目的地まで誘導する未来。視覚障がい者の移動支援ロボットを開発へ ハフポスト(2020年)
2024年、
画像引用・参考:AIスーツケースの社会実装による共生社会の実現を目指し、「一般社団法人次世代移動支援技術開発コンソーシアム」の活動を1年延長へ PR TIMES(2023年)
2017年の1年後に完成した初めての試作品は、金属フレームで組み立てた箱にバッテリーとモーターを詰め込み、パソコンを搭載したものでした。モーターを冷ますファンの音が外に響き渡り、浅川さんは「掃除機を持っているんじゃないかと周りの人から言われました」と、苦笑いをしました。
最初は、人の行列や流れを把握して停止させるのは簡単ではなく、何度もものにぶつかりそうになりました。スーツケースの形状に近づけようとすると走行時にバランスを崩し、工夫を図ることが必要となりました。
そこで制御機器大手「オムロン」など賛同する企業との連携も仰ぎながら、改良を重ね、大阪・関西万博会場での実証実験に漕ぎ着けました。6ヵ月間の会期中、複数台を配置します。
実証実験では、屋外の運用が大きな課題です。近くに建物がない場所では現在地の把握が困難です。GPSより精度の高い衛星測位方式を採用し、誤差を5~10cmに抑えることを掲げています。
テストでは、混雑している時に停止時間が長くなるデータが取れていて、人の行列や流れをどう認識し、円滑に案内するかが成否を握ります。
参考:「AIスーツケース」は世界へ連れ出す私の目…日本科学未来館長・浅川智恵子さん 読売新聞(2024年)
2025年、
画像引用・参考:視覚障がい者向け自律型誘導ロボット「AIスーツケース」大阪・関西万博での実証実験を実施 PR TIMES(2024年)
ハンドル部には、触ると現在の進行方向を確認できる方向提示装置を設置しました。また低い位置にある障害物を認識できる様に複数のLiDARセンサーを追加し、段差の乗り越え性能が上がる新しい車輪機構も採用しました。
これから、施設やパビリオンに関して、『AIスーツケース』を利用する方からの質問に答える機能や、対話から『AIスーツケース』を利用する方の興味を推測し、オススメの行き先を提案できる機能なども開発する予定です。
参考:デザイン一新、機能を追加した新型「AIスーツケース」、大阪・関西万博で実証実験 ITmedia NEWS(2025年)
浅川さんは、
「万博は『AIスーツケース』を世界へと羽ばたく良いきっかけ」
と力を込め、
「全世代の方が一人で移動もできて、楽しみながら移動できる、そういう世界が広がっていけばいいですね」
と述べ、将来的には機器を小型化し、文字通り『AIスーツケース』が視覚障害を抱えている人の案内役となれる、そんな未来を思い描いています。
1番最初に書いた時と違う気持ちを感じた
最初に『AIスーツケース』に関して書いた時は、1記事書くのもアップアップしていて、技術などもなく、書いた時の記憶にない位、とても苦労して書きました。
あれから約3年。記事自体は2021年に書いていたのですが、2022年に掲載された時より、随分操作方法とか、搭載された技術とか、格段と上がったなと感じました。
この記事を書いて、開発当時から、大阪・関西万博での活用を意識されていたそうですが、実際にそれが実現し、世界中の人の力を借りて、『AIスーツケース』が、さらなる発展と飛躍をするかもしれない。
2024年9月、浅川さんは、大阪・関西万博会場に整備された環状の大屋根(リング)の上に立ちました。槌音(つちおと)が響く中、心地よい風が吹き抜け、広々とした空間を感じました。「カモメが飛んでいるのかも」「海が見えるのかな」とイメージが沸々と湧いていって、
「障害が有る無しに関わらず、皆さんにとってかけがえのない体験ができる場所になるでしょう」と、予感は確信となりました。
とも書いてありました。
日本で開発された『AIスーツケース』が、世界中で、視覚障害を抱えている人の足となり、移動手段の1つとなる、そんな未来がもう、すぐそこまで迫っていることに、ワクワクします。
noteでも書いています。よければ読んでください。
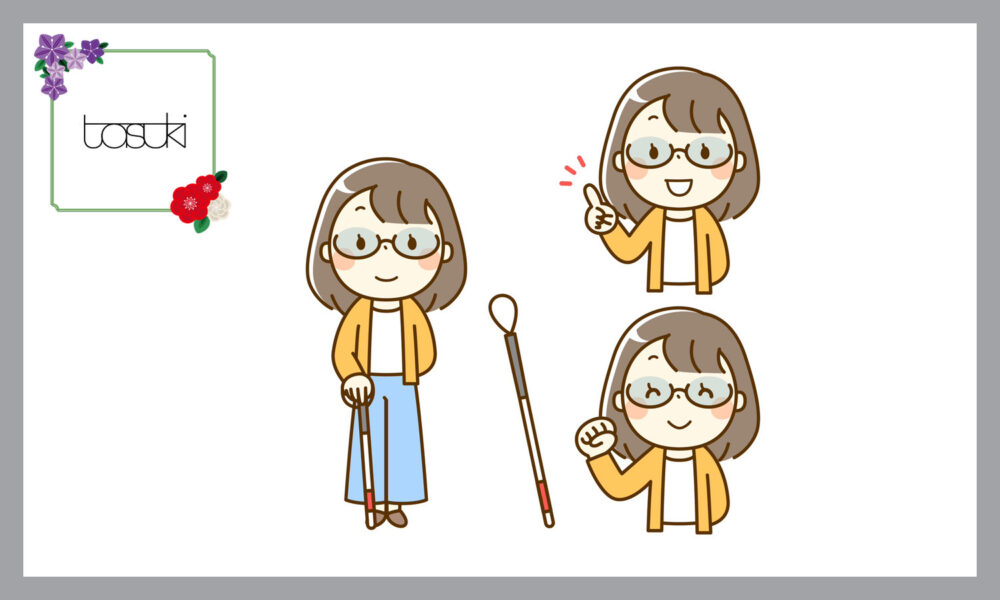

























コメントを残す