この記事は約 9 分で読むことができます。
まだまだ語りきれない、「児童養護施設について」のインタビューですが、いよいよ後編となりました!
【前編はこちらから】
(宮本)改めましてTANOSHIKAで職業指導員をしております、宮本と申します。
まず2024年の4月にケアリーバーの年齢の上限が解放されます。という政策自体の変更があったんですけど、これに関してはまだメリットとか保守的話題に関してはまだまだかなと思うんです。
例えば原口さんがこういった法改正があればとか、こういったことがネックで、とか行政に求めること、こういったことがあったらいいのにな、とかをお聞かせ願えたらと思います。
(原口)まだまだ施設だからというのが、古くからある制度ではあるのですけれども、私としては子供たちが「携帯を持つ」のが当たり前になってきて、全国的には結構、子供たちに携帯を持たせないといけない。となってまして、携帯会社とかも別の子たちに携帯を持ってもらって、それに合ったプランを出していただいたりしてるんです。
佐賀県がまだそういった取り組みに動き出せてなくて、子供たちが携帯を持っているところが、全国的に措置費から出していいよ。というところはあるのですけれども、その取り組みに進めれていないというのが現状なんです。
子供たちもアルバイトをしないと、携帯代を払えない。といったところがあるのですけれど、そこをバイトをしないでも携帯を持たせれるように、子供たちも今の時代、携帯を持っていないだけで疎外される場合もあるので、どうにかこうにかして緩和できればいいかな、と思っております。

(宮本)県だと久留米市が特に力が入っているんですけれど、包括支援という部分で私、今こちらのA型就労支援で務めさせていただいているんですけれど、その他にも子ども食堂とか生活困窮者の路地生活者の活動とかもやっているんですけど、やはり横のつながりって大事だと思ってて、施設でもなんでもいいんですけど、こういうところでもう少し子供たちに、将来性や融通が効くような見学とか可能性が広がる「繋がったらいいな」と思うような活動があったら教えていただきたいです。
(原口)やっぱいろんな経験をしてほしいな、というところはあります。
それこそ職業体験じゃないですけれど、今NPOの「ブリッジフォースマイル」の方が支援してくださって、職業体験だったり、自立に向けての活動だったりサポートについての活動がメインだったりするんですけれど、それ以外にも子供たちの職業体験だったり、学ぶ機会だというのは増やしていきたいな。とは思います。
そうやって支えていける団体だったりあればどんどん関わっていきたいなとは思っております。
【NPOブリッジスフォーマイル様】
(島川)職業指導員の島川です。世間の人に「こういうことを知ってほしいな、考えてほしいな」とか、そういったことは先生的には何かございますでしょうか。
(原口)やはり先ほども申し上げたんですけれど、施設に対する偏見ていうのは、世間的にはさほどないかなとは思うんですけれど、どうしても子供たち自身が施設で生活しているということを隠したり、特に中高生ですけれども授業参観に「来ないで」と言ったりなどがあります。
もうちょっと認知してもらって、施設に行ってて可哀想という偏見が減ったらいいなとは思っておりますね。
(島川)私も児童相談所の一時保護所というところで働いていた時がありまして、同じような境遇の方が、一瞬入ってはまたそういう施設に行ったりとか、いわば中継地点のような同じように困っている人達ではあるのですけれど、皆さん普通ですよね。
その子が取り巻く状況が普通じゃないだけであって、その子たちは特に何か問題があるわけじゃないですからね。
何かもしそういう誤解がされているんなら僕も解いていきたい。と思っているんで、そういう誤解を解いていきたい、少しでも力になれることがあれば、と思っています。
僕はあまり詳しくはないんですが里親制度ってあるじゃないですか、使っていって社会に出る人たちってただただ施設にいるよりはいい効果やいい影響はあるんじゃないでしょうか。
(原口)やっぱりより家庭的な支援といいますか、里親さんだと個別に関わってもらえるのがメリットと言いますか、そういったところに繋がっているんじゃないかとは思います。
例えば小さいころから本当ずっと施設に預けられている子、施設の生活しか知らない子っていうところを里親の一般家庭で生活をしてそれがガチっとハマることもあればそうでもなくて、また施設に戻って来たりする子もおりますので、一概に里親がいい、個別の関わりがいい、とういうのは私はそうでもないかなと思います。
(島川)「いい人にとってはいいし」という感じでしょうか。
(原口)里親さんと子供のマッチングと言いますか、そういうのをしっかり経て、しっかり時間をかけてマッチングをしっかりしないと、どうしてもそういった子供や里親さんの疲弊にもつながりますし、そこはかなり慎重にしないといけないところかなと感じています。
(島川)そうですよね、中々難しいだろうなと聞いていたんですが、あるほうがいい時はやっぱりあるんだろうな、と思います。
(原口)そうですね。
(島川)また別のインタビューの時に、施設出身の人があいさつの習慣が全然なくて「おはよう」「次これだよ」と言ってくれるからそれをやって、やっぱり生活や挨拶をする習慣がなかったからそういうパターンになっちゃっう子もいて、「当たり前の家庭」って知らずに育ったことによる弊害というのもどっかにあるのかもしれないですね
(どんはれ)佐賀県が里親制度とかに力を入れてるってことは地域にとって特色があったりするんですか。
(原口)たぶん全国的に里親制度に関しては「どう取り組んでいこうか」という話にはなるのですが、たぶん佐賀県自体の数値的に、里親委託率が多いのは、そもそも人数自体が少ないということもあります。
その分数値が上がっているんじゃないか、とも思います。
どの県も佐賀も、里親の研修はしっかりしているところはありますし、そういった制度の活用はどの都道府県でも実際に行われているのではないか、と思います。
(Pink)里親制度について勉強不足で申し訳ないのですが、子供が欲しくてもあまりできなくて、その時に里親制度のことについていろいろ聞いたんですけれども、海外とかではよく耳にするんですが、里親制度というのは年齢というのはあるのでしょうか。
(原口)その方たちの心意気と言いますか、気持ちに関わってくると思うんですが、里親になるにあたっての里親制度を取り入れつつ、まずは児童相談所とか地域の里親支援センターとかで、まずこういった制度の説明があり、そのあと研修を受ける。
で、実際に実習をしてみたりして、それで里親になるというのが一つのルートあるので、そこで感じられて「やっぱり里親になれないな」とかはあるかと思います。
なので「絶対なれない」とか「簡単にできる」とかそういったところはないなとは思いますね。
(Salad)では、そろそろお時間ですので、最後になりますが、私から原口先生にお礼を言いたいと思います。
私が今回このインタビューをしたいなと思ったのは、やっぱり私も児童を施設に預けるってなった時、すごい偏見を持っていたんですけど、例えば実際、帰省がある時に迎えに行くと他の施設の子たち「あ、●●ちゃん来たよ~」とか言ってくれたりとか、全然普通の子たちが普通にいる空間なんだなと思っていたんです。
これをどうにか発信していきたいなと思っていた時に、この企画を思いつきました。
今回本当にこのような場所をもうけさせていただいて本当にありがとうございます。
私が知っていてほしかったのは、本当に施設にいる子は普通の子なんですよ。
何にも悲しいことがないし、施設に帰ってくるときは「ただいま〜」なんて言ったり、家庭と同じような関わりを持っていたんだし、もっと多くの人に知ってほしい。施設というのは全然窮屈な場所じゃない。
施設に入ることで、もしそれで助けられるような子供がいたら、助けにもなるし、施設にいれるところを迷っている家庭というのもありますし、そういうときは頼ってもいいのかな。と思いました。
原口先生にもお世話になって、この場をもうけさせていただきました。
すみません長々と、ありがとうございました。
(原口)いえいえそんな、私でよかったのかなと思いますし。また次回こういう機会をもうけさせていただいた場合は園長を出しますんで。(笑)
さいごに
私が「児童養護施設」を知ることとなったのは、もう10年以上前になります。
当時、実家に妹とその子ども(甥、姪)と暮らしていましたが、妹のアルコール依存がひどく、子どもたちは、育児放棄されていました。
私自身も、フルタイムで働いており(しかもシフト制)帰りは、遅いと22時をすぎることもざらでした。
寝たきりの母親、肝臓を壊してこちらもほとんど寝たきりの父、アルコール依存の妹。
その子どもたち。と、抱えるものが多すぎて、爆発しそうになっていたその時、「児童養護施設」のことをネットで知ることとなりました。
このままでは、いけない。
子どもたちだけでも、助けないと。と思い、即役所に相談し、その週の内に児童養護施設で保護していただくことがきまりました。
何もしらない子どもたちを施設に送り届けるときに、泣くのを一生懸命に堪えたのを覚えています。
しかし、実際に養護施設に行ってみると、明るく開放的で、施設の職員さんたちは、すごく親切に子どもたちのこれまでのことを聞いてくださいました。
そこから、施設での生活は10年以上になっているのですが、私はこれでよかったと思っています。
敏感で繊細な子ども時代を、さみしい思いはさせたかもしれませんが、大きく傷つけることなく、過ごすことができました。
多くの先生方には、本当に感謝してもしきれません。
この場で改めてお礼を言いたいです。
うちの甥、姪を守ってくださいまして、ありがとうございます。
【関連記事】
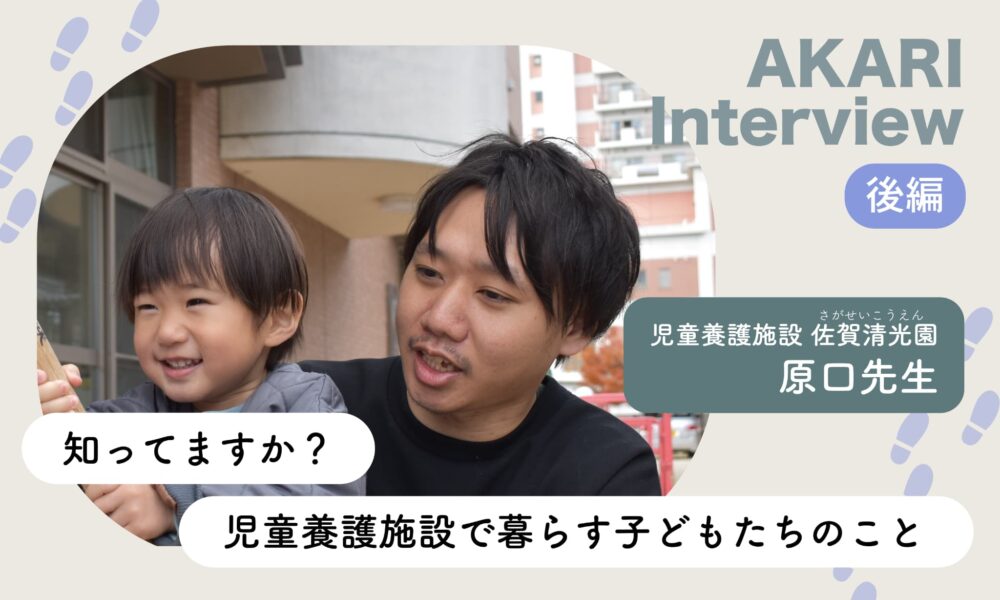



















コメントを残す